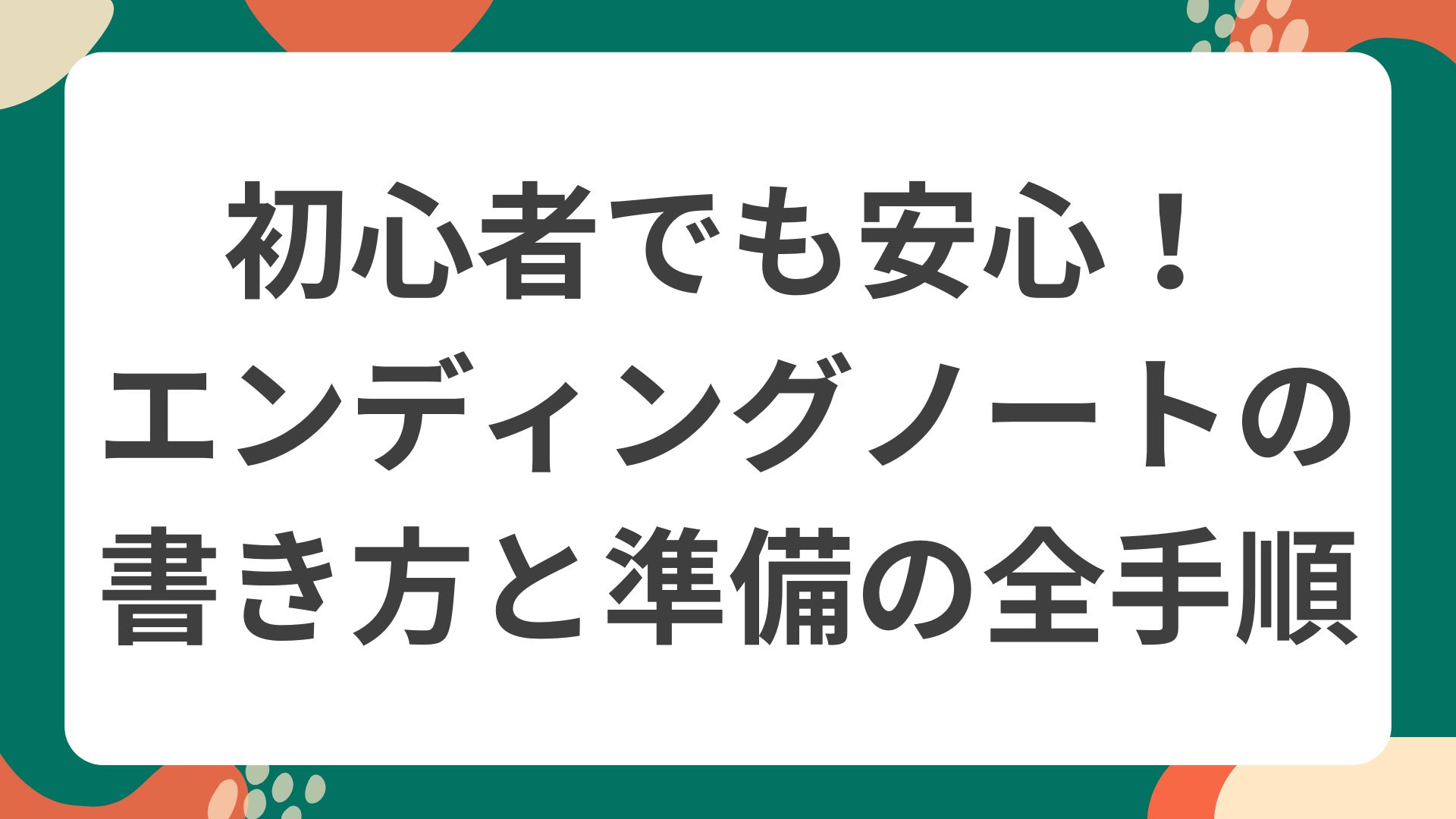
人生の最期を見据えて、自分の思いや大切な情報を残す手段として注目されているのがエンディングノートです。とはいえ、いざ書こうとすると「何から始めればいいのか」「どう書けばいいのか」と悩む人も少なくありません。エンディングノートの書き方には法的な決まりがなく、自由であるがゆえに戸惑ってしまうこともあります。この記事では、初心者でも無理なく取り組めるエンディングノートの書き方を丁寧に解説し、準備のステップや書く際のコツ、注意点までわかりやすく紹介しています。自分らしい形で思いを残すための第一歩として、ぜひ参考にしてください。
記事のポイント
- エンディングノートの基本構成と記入すべき主な項目
- 書き始める前に必要な準備と注意点
- 書きやすくするための具体的な工夫やコツ
- 自分に合ったエンディングノートの選び方と購入方法
エンディングノートの書き方を基本からわかりやすく解説
初心者でも安心!エンディングノートの正しい書き方とは
エンディングノートは、自分の人生の終わりに向けて大切な情報や想いを整理するためのものです。とはいえ、初めて書く人にとっては「何から始めればいいのか」「書き方に決まりがあるのか」といった不安を感じることもあるでしょう。
まず知っておきたいのは、エンディングノートに明確な決まりはないということです。法的な効力はないため、形式に縛られる必要はありません。大切なのは、読む人にとって分かりやすく、伝えたいことがしっかりと記されていることです。
一般的には、冒頭に自分の基本情報(氏名・生年月日・住所など)を記載し、家族構成、資産の情報、医療や介護に関する希望、葬儀の方法、相続についての考え、メッセージなどを項目ごとに記録していきます。一度にすべてを書こうとせず、思いついたことから少しずつ記入していくのが負担を減らすコツです。
また、記入内容は定期的に見直すことが重要です。ライフステージや家族の状況が変われば、伝えたいことも変わってくる可能性があります。鉛筆や消せるペンを使っておけば、修正も簡単にできます。
誰かに見せることを前提にする必要はありませんが、保管場所は家族に知らせておくと安心です。いざというときに見つからなければ、せっかく書いても意味がなくなってしまいます。
書き方の講座を受けるメリットと選び方のポイント
自力で書くのが不安な場合、エンディングノートの書き方講座を活用するのも良い方法です。特に高齢の方や文章を書くのに苦手意識がある方にとっては、大きな助けになります。
講座を受ける最大のメリットは、専門家から直接アドバイスを受けられることです。何を書けばいいのか、どの順番で書くべきか、自分に合った内容の整理方法など、実例を交えながら丁寧に説明してもらえる点が魅力です。対面講座であれば、わからない点をその場で質問できるのも安心材料の一つです。
ただし、講座にも種類があります。市区町村やNPOが無料で開催するものから、民間企業が提供する有料講座までさまざまです。価格に差があるため、受講前に内容や講師の実績を確認しましょう。受講者の声や口コミを参考にするのもおすすめです。
また、単に情報を詰め込む講義形式ではなく、実際にノートを記入しながら進める実践型の講座を選ぶと、理解が深まりやすくなります。講座によっては、エンディングノートの現物が教材として付いてくる場合もあるため、手元に残る資料の有無も確認すると良いでしょう。
オンライン講座も増えており、場所を問わず自分のペースで学べる選択肢も広がっています。移動が難しい方や、周囲に知られずに進めたい方にも適しています。
失敗しないために知っておきたい準備と注意点
エンディングノートを書く前に、いくつかの準備をしておくことで、後悔のない内容に仕上がります。まず取りかかる前に、自分が何を伝えたいのかを大まかに整理してみてください。たとえば、家族への想いや財産の分け方、医療の希望など、大切にしたいポイントを紙に書き出すだけでも構いません。
次に注意すべきは、情報の正確さです。特に財産や保険、金融機関に関する項目は、古い情報のまま記載してしまうと、かえって混乱を招く可能性があります。定期的な見直しが前提となることを意識して、更新しやすいように簡潔なメモ形式で書いておくと扱いやすくなります。
また、家族に関する記述には慎重さが求められます。特定の人に偏った感情を伝えすぎると、かえってトラブルの火種になることもあるため、伝えたいことは冷静な表現を心がけましょう。
さらに、エンディングノートは保管場所が重要です。誰にも見せたくないからといって隠してしまうと、いざというときに家族が見つけられません。鍵付きの引き出しや、保険証の近くなど、家族が自然に気づける場所に置いておくのが無難です。
書く内容が明確になっていない状態で始めてしまうと、途中で手が止まってしまうケースもあります。完璧を求めず、「とりあえず書き始めて、後から直せばいい」と思える心構えも、スムーズな作成には欠かせません。
書きやすさが変わる!エンディングノート作成のコツ
エンディングノートは一気に書き上げるものではなく、少しずつ完成を目指す方が現実的です。時間をかけて、自分の言葉でゆっくり書くことで、内容にも深みが出ます。焦らず、気が向いたときに1ページずつ書くことをおすすめします。
書く際のコツとしてまず挙げられるのは、テーマごとに章立てされているノートを使うことです。例えば、「医療・介護」「葬儀」「財産」「家族へのメッセージ」など、カテゴリが分かれていれば、自分が書きやすい項目から手をつけやすくなります。
また、言葉選びに迷ったら、箇条書きを活用しましょう。文章にするのが苦手な方でも、ポイントだけを簡潔に並べておくだけで伝わりやすくなります。長文にこだわる必要はありません。
使用する筆記具にも気を配ると作業がはかどります。消せるボールペンや鉛筆であれば、書き直しも簡単です。気軽に修正できるという安心感があると、心理的なハードルも下がります。
さらに、書いた内容が他人にとって分かりにくくならないよう、具体的な言い回しを心がけましょう。たとえば「子どもたちへ」ではなく、「長男の○○へ」と名前を入れることで、誰に向けた内容かがはっきりします。
作成後は、書いた内容が偏っていないか、家族の状況や価値観に配慮されているかも見直してみてください。客観的な視点で読み返すことで、より伝わるノートになります。
人気のエンディングノートに共通する使いやすさの秘密
よく選ばれているエンディングノートには、いくつかの共通点があります。最も大きな特徴は、初めて手に取る人でも取り組みやすい設計になっていることです。たとえば、質問形式で記入を促すタイプのものは、何を書けばいいか迷ってしまう人にとって心強い存在になります。
また、色分けされたインデックスや見やすいフォントが使われているものは、読み返すときの負担が少なく、家族にとっても理解しやすくなります。視覚的な配慮は、内容を正確に伝える上でも大きな助けになります。
そして、ノート全体に一貫した構成があることも大きなポイントです。医療、葬儀、相続、メッセージといった内容が順を追って並んでいると、頭の中も整理しやすくなり、無理なく書き進めることができます。
さらに、記入欄に余白が多めに取られているノートは、あとから情報を追加したいときにも便利です。生活の変化や気持ちの変化に応じて何度でも見直せるような柔軟さは、長く使っていく上で欠かせません。
文字を書くことに自信がない人でも、イラストやチェックボックスで記入できるタイプを選べば、自分の意思を伝えるハードルは大きく下がります。選ぶときには、内容だけでなく使う側の気持ちに寄り添った作りかどうかも、しっかり確認してみてください。
書き方に悩まないためのおすすめテンプレート活用法
何から書き始めればいいか迷ってしまうときは、テンプレートを活用するのが効果的です。特にフォーマットが整っているテンプレートは、項目ごとに書き込むだけでエンディングノートとしての体裁が整うため、手間も時間も大きく省けます。
たとえば、「私について」「家族について」「もしものときに備えて」といった具体的な見出しがあるテンプレートなら、自分に関係ある部分だけを選んで書いていけるため、途中で行き詰まる心配が少なくなります。
テンプレートの魅力は、書き漏れが起きにくい点にもあります。自分ひとりでは思いつかない内容も、テンプレートを通じて自然に浮かび上がってくることがよくあります。必要な情報が網羅されている形式を選べば、安心感も得られるでしょう。
活用の際は、テンプレートの文言をそのまま写すのではなく、自分の言葉に置き換えるよう心がけてください。たとえ短い言葉でも、自分らしさが加わることで、読む側の印象は大きく変わります。
書き直しを前提にするなら、紙に直接記入するよりも、パソコンで入力できるテンプレートを選ぶのも一つの手です。保存しながら少しずつ進められるため、気軽に取り組みたい人にも向いています。
テンプレートは多くの種類がありますが、迷ったときには医療や介護、葬儀、財産など、人生の終わりに関わる基本的な項目が含まれているかどうかを基準にしてみてください。選び方ひとつで、書くときのストレスは大きく変わります。
自分に合ったエンディングノートの書き方と選び方ガイド
エンディングノートはどこで買える?購入方法を徹底比較
エンディングノートを購入できる場所は、いくつかの選択肢があります。どの方法にも利点と注意点があるため、目的に応じて選ぶことが大切です。
まず、実店舗では大手の書店や文具専門店が候補になります。店頭で中身を確認しながら選べるため、初めて購入する方には安心です。ただ、品揃えは店舗によって異なるため、複数の店を見て回る必要が出てくることもあります。
次に、インターネット通販を利用する方法があります。通販サイトでは種類が豊富で、価格帯や内容を比較しやすいのが特徴です。ただし、実際に手に取って確認できないため、購入後に「思っていた内容と違った」と感じることもあるかもしれません。
もうひとつの選択肢として、100円ショップでも手軽に購入できるタイプのエンディングノートがあります。必要最低限の内容がまとめられているため、まずは試してみたい人にはぴったりです。ただし、内容が簡略化されていることが多く、詳細に書きたい人には不向きです。
このほか、自治体や葬儀社などが無料で配布しているケースもあります。公共機関が作成しているものは、地域の制度や手続きに即した内容になっていることも多く、実用性を重視する人にとっては有効な選択肢となります。
機能と価格のバランスで選ぶエンディングノートの選び方
エンディングノートを選ぶ際には、機能と価格のバランスを見極めることが大切です。価格が高ければ良いというわけではなく、必要な内容がしっかり含まれているかどうかが判断のポイントになります。
まず確認したいのは、どのような記入項目が用意されているかです。医療・介護・葬儀・財産など、自分が書いておきたい分野がきちんと網羅されているかを見ておきましょう。全体が簡潔にまとめられているものもあれば、細かい質問形式で掘り下げられているものもあります。
書きやすさも重要な要素です。ページの構成が分かりやすいか、紙質や行間がちょうどよいか、書き込むスペースが足りるかなど、細かな部分が後の使い勝手を大きく左右します。
価格帯は数百円の手軽なものから、しっかりと装丁された高価格帯の商品まで幅広く展開されています。高価なものほど項目が充実していたり、表紙が丈夫だったりしますが、予算と必要性をよく考えて選ぶことが肝心です。
また、後から書き直したり情報を更新したりできるように、バインダー式になっているかどうかも確認ポイントです。ページが固定されているものは一度書いた内容を修正しにくいため、何度も見直したい人には向きません。
自分が何を記録したいか、どれくらいの情報量を残したいかを明確にしながら、内容と価格が釣り合ったものを選ぶようにしましょう。
書き方の講座付きエンディングノートは本当にお得?
書き方の講座がセットになっているエンディングノートは、内容をしっかり理解して書き進めたい人には心強い存在です。特に、「何から書けばいいのかわからない」と感じる初心者にとっては、手引きがあることで不安が大きく軽減されます。
講座では、ノートの構成や書き方の基本だけでなく、項目ごとに考えるべき視点や記入時の注意点なども詳しく解説されることが多いです。質問ができる形式であれば、自分の状況に合ったアドバイスを受けることも可能です。
ただし、すべての人にとってお得とは限りません。すでにエンディングノートの目的を理解していて、迷わず記入できる人にとっては、講座の内容が重複して感じられることもあります。また、講座費用が商品価格に含まれているため、ノート単体と比べてやや高めになる点も考慮が必要です。
自分で調べながら進めることに不安がある場合は、こうした講座付きの商品を活用することでスムーズに作成できます。一方で、ある程度の知識がある人には、自分のペースで書けるシンプルなノートの方が合っている場合もあります。
専門家も推薦!おすすめエンディングノート3選
選ばれているエンディングノートには、使いやすさや情報整理のしやすさなど、共通した特徴があります。中でも専門家がすすめるノートには、実務での利用も想定した工夫が随所に見られます。
まずひとつ目は、項目がジャンル別にしっかり分かれており、生活や資産、医療などの情報を体系的に記入できるものです。必要なときに必要な情報だけを確認しやすく、家族にとっても使い勝手が良い構成になっています。
次に注目されているのが、書き手の思いを丁寧に伝えられるよう、自由記述欄が多めに設けられているノートです。事務的な情報だけでなく、自分の考えや希望を具体的に残しておきたい人に適しています。
三つ目は、記入しやすさに特化したノートです。紙質やレイアウトにこだわりがあり、ボールペンでも裏写りしにくく、書きやすさがストレスになりません。文字を書くことに慣れていない人でも取り組みやすいよう配慮されています。
選ぶ際には、自分にとって必要な機能が備わっているかを見極め、見た目や雰囲気よりも「書きやすさ」と「活用しやすさ」を重視することが大切です。
書きやすさと実用性で選ばれる人気エンディングノートとは
多くの人に選ばれているエンディングノートには、手に取りやすさと、実際に使うときの便利さが備わっています。特に人気のあるタイプは、記入欄が広すぎず狭すぎず、バランスよく構成されているものです。必要な情報がどこにあるかすぐにわかるページ設計も、支持される大きな理由です。
例えば、目次が明確で、医療・介護・財産などの情報が見出しごとに整理されていると、記入中も見直すときも迷いません。また、項目ごとに記入例があると、何を書けばよいのか具体的にイメージしやすくなります。
実用性という点では、保管方法まで配慮されたノートが注目されています。たとえば、耐久性のある紙を使っていたり、記入後に家族が探しやすいように目立つ色や表紙デザインが工夫されていたりするものもあります。
さらに、必要な項目が網羅されつつも、途中で負担に感じにくいボリュームで構成されているノートが選ばれやすい傾向にあります。気軽に書き始めやすく、継続して書ける工夫がされているかがポイントになります。
後悔しないためのノート選びと書き方のコツ
エンディングノートを書き始める際、多くの人が迷うのが「どのノートを選べばいいか」と「どう書けばいいか」という2点です。失敗しないためには、最初に自分の目的や家族の状況に合ったノートを選ぶことが大切です。
内容をすべて網羅したい人には、全項目が細かく用意されたノートが向いています。一方で、最低限の情報だけを簡潔にまとめたい場合は、必要な部分だけ書けるシンプルな形式のものが適しています。途中で書くのが億劫にならないよう、最初から欲張らずに選ぶことも一つの方法です。
書き方については、一気にすべてを埋めようとせず、日を分けて少しずつ進めるのがコツです。まずは記入しやすい内容から始めて、自分の考えが整理されてから他の項目に移るようにすると、途中で止まってしまうことを防げます。
また、項目によっては「書いておきたくない」「まだ決めきれない」と感じる部分もあるかもしれません。そうしたときは、無理に埋めようとせず、余白を残しておくことも大切です。ノートは完成させることが目的ではなく、自分の思いや情報を残す手段であるという意識を持つと、取り組みやすくなります。
書き方に迷ったときのヒントになる実例と参考情報
エンディングノートの記入を進めていると、「この項目はどう書けばいいのか」と立ち止まってしまう場面があります。特に、介護や葬儀に関する希望、自分の想いを伝える欄では、書き方に悩む人が少なくありません。
そうしたときに役立つのが、実際に書かれた例や記入の参考になるフォーマットです。例えば、「延命治療を希望するかどうか」の欄には、「家族の負担を減らすため、延命処置は希望しません」といったように、自分の意思とその背景を一緒に書くと、読む人にとっても理解しやすくなります。
また、「財産について」の項目では、すべてを細かく書かなくても、保有している金融機関名と大まかな内訳だけでも記入しておくと、家族が手続きをする際に役立ちます。詳細は別紙にまとめて添付しても問題ありません。
もし文章にするのが難しい場合は、箇条書きを活用するとハードルが下がります。内容の優先度がはっきりしていれば、整理しやすくなります。あらかじめ決められた記入例やテンプレートが用意されているノートを選ぶのも、迷いを減らす方法のひとつです。
さらに、市販のノートに付属するガイドブックや、自治体が配布している記入サンプルなども参考になります。無理に一人で完成させようとせず、身近な資料を活用しながら、自分の言葉で少しずつ進めていくことが大切です。
ライフストーリーを使ってあなたの人生を記録してみませんか
「ライフストーリー」とは家族や家系の記憶をあなたが次世代へ受け継ぐことができるサービスです。
遺書や遺言書とは異なる新しい形のエンディングノートです。
無料プランも用意されておりますので、まずは登録して使ってみてください!
\無料登録はコチラから/
