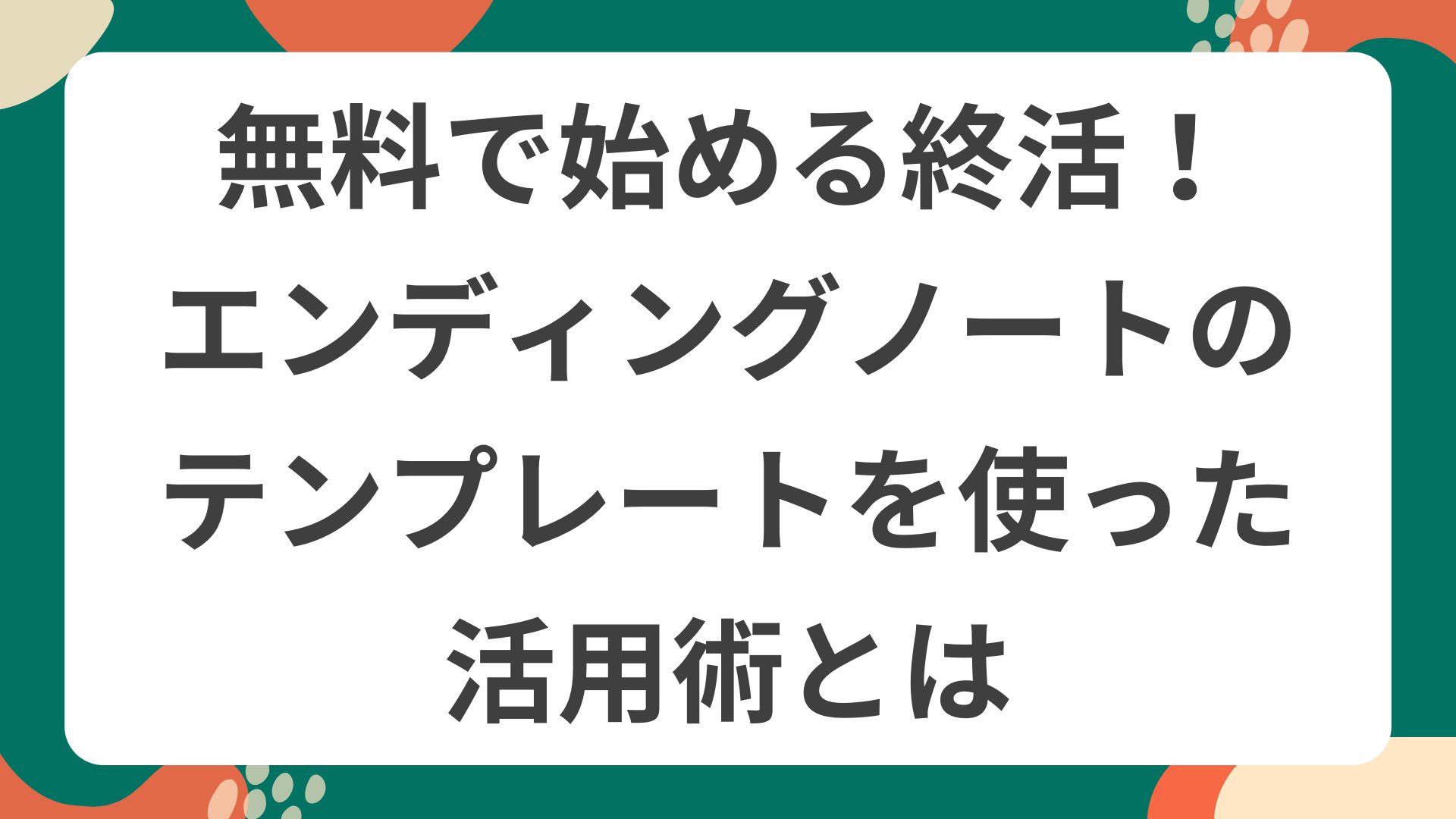
終活を考え始めたとき、最初の一歩として多くの人が選ぶのがエンディングノートです。しかし、「どこで手に入れるのか」「どう書けばいいのか」といった不安を感じている方も少なくありません。そんなときに役立つのが、無料でダウンロードできるエンディングノートのテンプレートです。この記事では、エンディングノートテンプレートの種類や選び方、PDFやExcelといった形式ごとの特徴、さらには家族と共有しやすい活用方法まで詳しく解説していきます。あなたに合ったテンプレートを見つけて、無理なく終活を始めてみましょう。
記事のポイント
- エンディングノートテンプレートの主な種類と形式
- 自治体や企業が提供するテンプレートの特徴
- PDF版とExcel版のメリット・デメリットの違い
- 自分に合ったテンプレートの選び方と活用法
エンディングノートのテンプレートを無料で手に入れる方法とは?
無料で配布されているテンプレートの種類と入手先
エンディングノートのテンプレートは、実はさまざまな団体や企業、個人サイトで無料配布されています。特に注目すべきは、配布元によって内容や形式に違いがある点です。
まず、配布されている形式には主にPDF版とExcel・Wordといった編集可能なデジタル形式があります。PDF版は手書きに適しており、印刷して使うことを前提としています。一方、ExcelやWord形式はパソコンで直接入力ができるため、デジタル管理をしたい方に向いています。
提供元の種類もいくつかに分かれます。代表的なのは自治体、終活サービスを提供している企業、法律事務所、税理士事務所、そして個人のブログなどです。自治体は地域に根ざした内容を盛り込み、相談窓口の案内も充実している傾向があります。企業はサービス案内を含めつつも、ユーザーにとって実用的なテンプレートを提供していることが多いです。法律や税務の専門家が配布するものは、相続や財産管理の項目が特に細かく設計されています。
入手方法は簡単です。多くの場合、該当のホームページからワンクリックでダウンロードできます。ただし、中には名前やメールアドレスの登録が必要なケースもあります。これにより広告メールが届くこともあるため、登録前に注意書きをよく読みましょう。
スマートフォンよりパソコンからのダウンロードのほうがスムーズに進む場合が多いため、操作に不安がある方は家族にサポートしてもらうのもひとつの方法です。
自治体が公開する安心のテンプレートを活用しよう
エンディングノートのテンプレートを選ぶ際に、もっとも安心できる選択肢のひとつが「自治体が配布しているもの」です。なぜなら、公的機関が制作しているため内容の信頼性が高く、地域密着型の情報も網羅されているからです。
自治体のテンプレートは、多くの場合、住民の高齢化を見据えた取り組みの一環として作成されています。そのため、終末期医療や介護、相続といった重要項目に加えて、地域の相談窓口や支援制度の情報が掲載されています。これにより、ノートに記入した内容をそのまま行政の窓口で相談できるというメリットがあります。
もうひとつの特徴は、テンプレートの構成が非常に丁寧で、質問形式やチェックリストが多く取り入れられている点です。記入の順番に悩むことなく、自然と必要事項を書き進められる工夫が施されています。
ただし、すべての自治体がテンプレートを用意しているわけではありません。市区町村によって取り組みの有無が異なり、同じ県内でも対応が分かれる場合があります。自治体の公式ホームページにPDFで公開されていることが多いため、まずはお住まいの地域名と「エンディングノート」で検索してみるのがおすすめです。
印刷コストがかかることや、文字が小さい場合もあるため、内容を確認してから印刷するようにしましょう。特に高齢の方に渡す場合は、読みやすさも重視して選んでください。
終活サービス会社が提供する独自テンプレートとは
終活サービスを展開する企業が作成したテンプレートは、ユーザーの使いやすさを意識した設計が多い点が特徴です。企業ごとに工夫が異なるため、他では見られない独自性が感じられます。
たとえば、一般的なエンディングノートは「書く内容が多すぎて何から始めればよいかわからない」と感じる方もいますが、企業のテンプレートでは章立てがわかりやすく、導入部分に「書き方のヒント」や「記入例」がついていることがあります。これにより、初めて記入する人でも迷いにくくなっています。
さらに、視認性にも配慮されている場合が多く、大きな文字やカラーの見出しを取り入れたデザインが採用されていることもあります。高齢者やパソコンに不慣れな方にも配慮された工夫といえるでしょう。
一方で、こうしたテンプレートの一部は、サービスの宣伝を兼ねて作られていることがあります。そのため、企業によっては会員登録やメールアドレスの提供が必要になるケースもあるため注意が必要です。
テンプレートそのものは無料であっても、将来的に有料プランへの誘導がある可能性もゼロではありません。必要以上の情報提供を避けたい場合は、登録の前に利用規約などを確認しておくと安心です。
PDF版テンプレートの魅力と使いやすさを徹底解説
PDF形式のテンプレートは、手軽さと見た目の整った仕上がりが魅力です。特に、パソコンやスマートフォンに慣れていない人でも扱いやすく、印刷してすぐに使える点が好まれています。
この形式のメリットのひとつは、レイアウトが崩れないことです。WordやExcelでは開く環境によって見た目が変わることがありますが、PDFはどの端末でも同じように表示されます。これにより、印刷した際の見栄えも安定し、記入ミスを減らすことにつながります。
また、PDFファイルは多くの端末で簡単に開くことができ、専用ソフトもほとんどの場合不要です。スマートフォンやタブレットでも閲覧可能なため、家族と画面を見ながら一緒に内容を確認することもできます。
ただし、PDFは基本的に直接入力できない形式であるため、記入には印刷が必要です。パソコン上での編集が必要な方にとっては、入力できるWordやExcelの方が向いているかもしれません。
加えて、印刷環境が整っていない家庭では、コンビニや印刷サービスの利用が必要になることもあります。全ページを印刷すると紙代やインク代がかかるため、必要なページだけを選んで印刷するなど、コストを意識した使い方が求められます。
PDF版は「紙で残したい」「読みやすさを重視したい」という方にとって、実用性の高い選択肢といえるでしょう。
Excel版テンプレートの便利な使い方と注意点
Excel版のテンプレートは、項目を自由に編集できる点が大きな強みです。名前や住所、財産情報など、自分に必要な項目だけを残して使えるため、細かいカスタマイズが可能です。
入力欄にすぐ文字を打ち込めるため、記入が速く進むだけでなく、何度でも修正できます。例えば、預金口座の内容が変わったときや、家族構成に変化があったときも、上書き保存するだけで更新が完了します。紙のように書き直す手間がかからず、手が疲れにくいという利点もあります。
ただし、Excelに不慣れな方にとっては操作が難しいと感じることもあるかもしれません。セルを間違って消してしまったり、フォーマットが崩れて見づらくなるケースもあります。そうした事態を防ぐために、編集前のテンプレートは必ずコピーをとって保存しておくと安心です。
また、入力したデータはパソコン内に保存されるため、データの紛失や漏えいのリスクも考慮する必要があります。USBメモリやクラウドにバックアップをとっておくほか、パスワードでファイルを保護するのも有効な対策です。
Excel版は慣れれば非常に使い勝手がよく、長期間の情報管理にも適していますが、最初は基本操作に時間をかけるつもりで取り組んだ方が失敗が少なく済みます。
手書き・パソコン・スマホ、どの方法で作成するのがベスト?
どの作成方法が適しているかは、使う人の性格や目的、生活環境によって変わります。どれが正解というより、自分にとって無理なく続けられる方法を選ぶことが大切です。
まず、手書きの方法は、紙に直接ペンで書くため、操作に自信がない方や、感情を込めて書きたい人に向いています。書いているうちに気持ちが整理されるという良さもあります。ただ、書き損じたときの修正が面倒だったり、繰り返しの更新に時間がかかる点はデメリットです。
一方、パソコンでの作成は、編集のしやすさが魅力です。文字の打ち込みが早く、保存や修正も簡単にできます。文章を整える機能も豊富で、見た目のきれいさにこだわりたい方にはぴったりです。ただし、操作ミスやパソコンの故障によるデータ消失に備えた対策は必要です。
スマートフォンは、いつでもどこでも操作できるという便利さがあります。外出先で気づいたことをメモしたり、家族に見せながら内容を相談するのにも適しています。ただ、画面が小さいため記入作業がしにくいと感じる人も少なくありません。長文を入力するにはやや不向きといえるでしょう。
それぞれの方法には良さと難しさがあるため、自分にとって使いやすい形式を試しながら選ぶことをおすすめします。作成が目的ではなく「伝えること」が目的であることを意識すると、手段の選び方も自然と見えてきます。
エンディングノートのテンプレートの選び方とおすすめ活用法
目的に合ったテンプレートを選ぶためのチェックポイント
テンプレートを選ぶ際は、ただ「書きやすいか」だけで決めてしまうのはもったいない話です。まずは、自分がどのような内容を記録したいのかを明確にしましょう。医療や介護の希望を細かく書きたい人と、財産管理をしっかりまとめたい人とでは、適したテンプレートが変わってきます。
例えば、医療に関する希望や延命治療についての記述を重視したいなら、医療機関が監修したテンプレートや介護向けに工夫された形式のものが安心です。一方で、相続や保険の情報を中心に記録したい場合は、税理士や司法書士が作成したテンプレートが向いています。中には「家族へのメッセージ」が中心となっている感情的な内容重視のものもあります。
次に確認すべきなのは、記入のしやすさです。文字の大きさ、行間の広さ、用語のわかりやすさなども重要です。デザイン性が高くても、専門用語が多いと書く手が止まってしまうことがあります。見た目よりも、使いやすさを優先してください。
また、デジタルで管理したいのか、それとも紙で残したいのかによって、ファイル形式の選択も変わってきます。最終的には家族に見てもらうことを前提に、どの形式で渡すのが一番伝わるかを想像して選ぶと失敗が少なくなります。
テンプレートは一度選んで終わりではありません。途中で違うものに切り替えても問題ありませんし、複数の形式を併用することも可能です。
PDF版とExcel版、それぞれのメリットとデメリット
PDF版とExcel版のテンプレートは、それぞれ特徴が異なるため、自分の状況に応じて選ぶことが大切です。
PDF版は見た目が整っており、開く端末によってレイアウトが変わることがないため、印刷用として非常に優れています。特に、パソコンに詳しくない方や、手書きで記入したい方には適した形式です。用紙にペンで書き込むことで、より実感を持って記録に向き合うことができるという声もあります。
ただし、PDF版は基本的にパソコン上での編集が難しく、内容を変更するたびに再印刷が必要になります。書き損じた場合は、最初から書き直すことになる可能性があるため、修正のしやすさには欠けるかもしれません。
一方、Excel版はデジタルでの記録や更新に非常に向いています。項目ごとに入力欄が分かれていることが多く、スムーズに書き進めることができます。修正も自由なので、財産や連絡先に変更があった場合でも簡単に対応可能です。色分けや罫線を加えることで、自分仕様にカスタマイズできる楽しさもあります。
ただ、Excelに不慣れな方には操作が難しく感じられることもあります。うっかりセルを削除してしまったり、フォーマットを壊してしまうことも考えられるため、使い慣れるまでには少し時間がかかるかもしれません。また、印刷を前提としたレイアウトにはなっていないことも多く、用紙に出力する際に手間取るケースもあります。
どちらにも良い点と難しさがありますが、書く目的と使う人のスキルを考慮すれば、自然と適した形式が見えてきます。
家族と共有するならどのテンプレートが安心?
家族と情報を共有することを前提にするなら、見やすさと扱いやすさを重視したテンプレートを選ぶのが最も安心です。誰が見ても内容が把握しやすく、必要な情報が整理されていることが大切です。
共有しやすい形式としては、PDF版とWord版のどちらかをおすすめします。PDFは印刷して渡すことができるため、紙で保管したい家族にも対応しやすいです。特に、高齢の家族がいる場合は、紙で読む方がスムーズに確認できる傾向があります。加えて、重要な部分にはマーカーで印をつけるなどの工夫も可能です。
Word版は、内容の編集や追記がしやすいため、進行中の話し合いや定期的な更新があるときに便利です。たとえば、介護の希望が変わったり、財産情報が追加された際にすぐ反映できます。家族が複数人いる場合は、共有用のクラウドストレージを使ってファイルを保存しておけば、誰でも同じ内容を確認できます。
ただし、共有する側と受け取る側のパソコン環境やITスキルが大きく異なることもあるため、渡し方には配慮が必要です。いくら見やすいテンプレートでも、相手が開けなければ意味がありません。形式を選ぶ際は、相手の使いやすさを最優先に考えてください。
また、内容の共有前には「これは誰に見せるものか」を家族間で確認しておくことも重要です。すべてをオープンにするのが適切とは限らず、個人の思いが含まれる項目もあるため、共有範囲はあらかじめ話し合って決めておきましょう。
テンプレートを使ったエンディングノートの書き進め方
テンプレートを手に入れた後、いざ書こうと思っても、どこから手をつけるべきか悩むことがあります。最初にすべきことは「書けそうなところから始める」ことです。順番通りに埋めていこうとすると、途中で詰まりやすくなります。
まずは、氏名や生年月日、住所といった基本的な情報から書いてみてください。これらは確認するだけで記入できる項目です。次に、自分の過去を振り返る「自分史」や「思い出」の欄に進むと、徐々に慣れてくるはずです。感情が動きやすい部分でもあるため、集中力が高まっているときに向いています。
財産の項目や医療・介護の希望など、判断に迷う内容は後回しにして構いません。特に、資産に関する部分は時間をかけて調査が必要になることもあります。少しずつ分けて記入していけば、気負わずに続けられます。
また、テンプレートには空白が多く用意されていることがあり、自分の言葉で自由に書ける欄が存在します。このスペースは、家族への感謝や伝えたい思いを書くのに適していますが、何を書けばいいか迷ったときは、日常の出来事や趣味について軽く触れても問題ありません。形式にとらわれず、自分のペースで記録を重ねていくことが大切です。
完成を急ぐ必要はありません。月に1〜2回など、定期的に時間をとって見直しながら書き進めると、内容の質も高まりやすくなります。焦らず、自分に合ったペースで続けてみてください。
デジタル保存で安心!エンディングノートの管理術
エンディングノートをデジタルで保管する方法は、紙に比べて手軽で安全性が高く、編集の自由度もあります。ただし、保存方法を間違えると、思わぬトラブルにつながることもあるため、基本を押さえておくことが重要です。
まず、保存先はパソコンのローカルだけに頼らないようにしましょう。ハードディスクが壊れたり、機器の入れ替えをしたときにデータが消えてしまう可能性があります。そこで役立つのがクラウドサービスの活用です。代表的なものではGoogleドライブやOneDriveなどがあり、インターネット経由で安全にデータを保管できます。スマホや別の端末からもアクセスできるため、外出先でも内容を確認できます。
次に、ファイル名にも工夫が必要です。単に「エンディングノート.xlsx」としてしまうと、後から見たときに内容や日付が分かりにくくなります。「2025_05_エンディングノート_最新版」といった具合に、作成日やバージョンを入れておくと管理しやすくなります。
さらに、セキュリティ対策も忘れてはいけません。大切な個人情報が詰まっているため、パスワード付きで保存することをおすすめします。PDFやWordには簡単に設定できる機能があります。また、家族にもその存在と保存場所を伝えておくと、必要なときにすぐ見つけてもらえます。
最後に、定期的な見直しも管理の一環です。半年に一度や年に一度のタイミングでファイルを開き、内容に変更がないか確認しておくと、常に最新の情報を家族に伝えられます。
迷ったらこれ!初心者におすすめのテンプレート5選
エンディングノートのテンプレートは種類が多すぎて、どれを使えばいいのか迷ってしまうことがあります。初めて取り組む方には、書きやすさと分かりやすさを兼ね備えたものがおすすめです。
ひとつ目は、医療や介護に関する質問項目が中心のテンプレートです。専門的な言葉を避けて、簡単な表現で希望を記入できる構成になっています。家族と相談しながら書くには最適です。
二つ目は、若い世代向けに作られたカジュアルなデザインのものです。例えば表紙がイラストになっていたり、記入欄が少なめだったりと、気軽に書き始めたい人に合っています。20代〜40代でも取り組みやすく、終活というより「これからの人生を整理する」感覚に近い構成です。
三つ目は、すべての記入項目が一覧で表示されているシンプルな表形式のテンプレートです。特にExcel版で作られたものは、データの管理が得意な人にとって非常に使いやすいです。不要な行を削除したり、必要な項目だけに絞って記入したりと自由度があります。
四つ目は、手書き前提で作られたPDF版です。大きな文字と広めの行間が特徴で、文字を大きく書きたい方や目の疲れが気になる方に向いています。ご両親や高齢のご家族にもすすめやすい形式です。
五つ目は、法律事務所や専門家が監修しているテンプレートです。相続や遺言に関する記入欄が細かく設けられているため、法的な整理も視野に入れている方には役立ちます。専門用語が出てくることもありますが、信頼性の高さがポイントです。
初心者の場合は、まずいくつかのテンプレートを見比べて、自分が「書き進められそう」と感じるものを選ぶことが大切です。構えすぎず、書きやすいものから始めてみてください。
ライフストーリーを使ってあなたの人生を記録してみませんか
「ライフストーリー」とは家族や家系の記憶をあなたが次世代へ受け継ぐことができるサービスです。
遺書や遺言書とは異なる新しい形のエンディングノートです。
無料プランも用意されておりますので、まずは登録して使ってみてください!
\無料登録はコチラから/
概略:無料で始める終活!エンディングノートのテンプレートを使った活用術のまとめ
