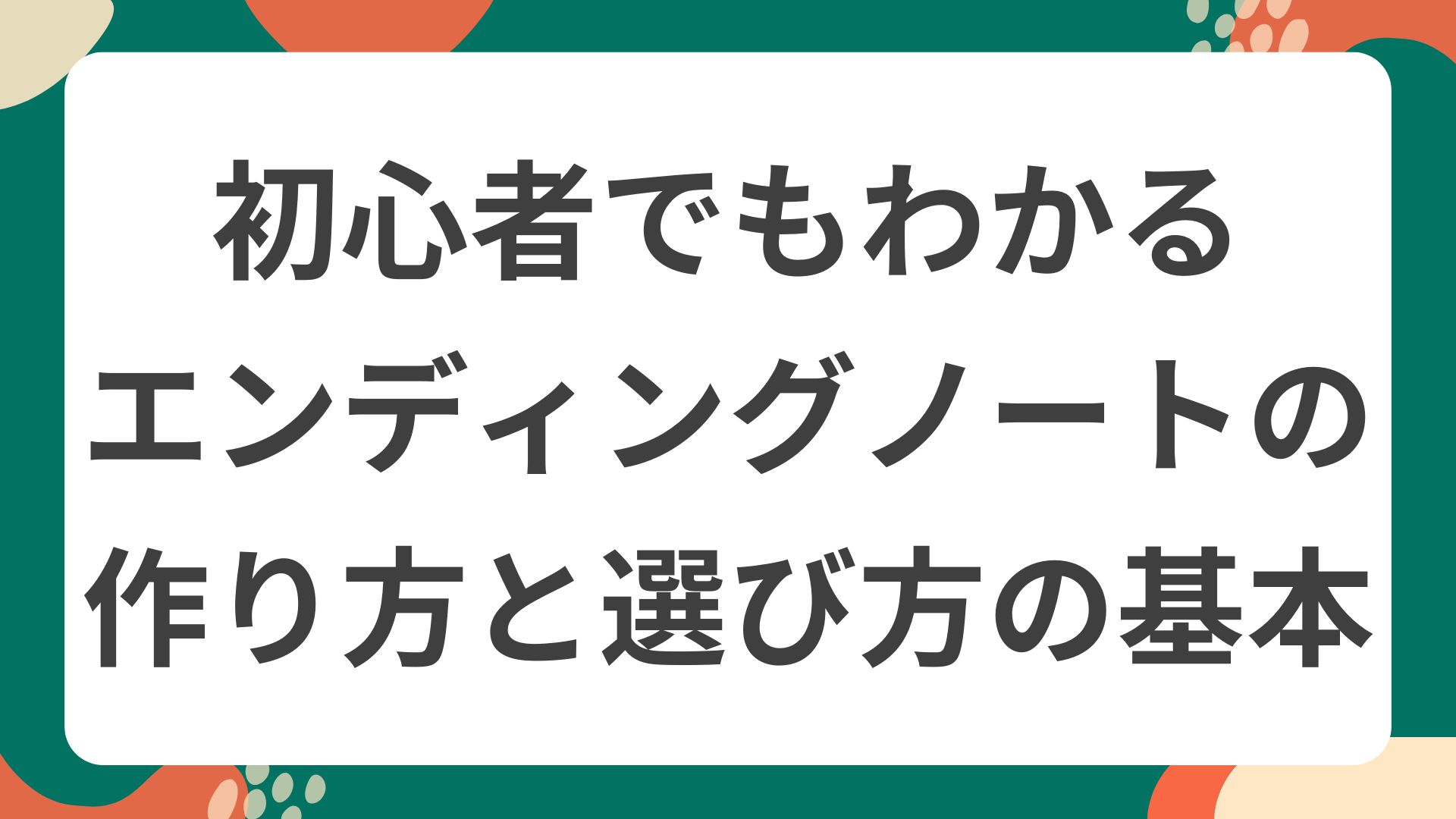
人生の終わりに向けた準備として注目されているのが、エンディングノートです。しかし、いざ書こうと思っても、何から始めてよいのか、どんな内容を書けばいいのか迷う人は少なくありません。エンディングノートの作り方には、基本の手順や押さえておきたいポイントがあり、それらを知っておくことでスムーズに書き進められるようになります。
この記事では、初心者でも取り組みやすいエンディングノートの作り方をわかりやすく解説しながら、自分に合ったノートの選び方や記入のコツについても紹介します。家族に伝えたい思いをしっかり残すためにも、無理なく始められる方法を知っておきましょう。
記事のポイント
- エンディングノートを作るための基本的な手順
- 自分に合ったエンディングノートの選び方
- 記入時のコツや続けやすくする工夫
- 市販・自作・無料のノートの違いや特徴
初めての方でも安心!エンディングノートの作り方の基本ガイド
エンディングノートはどうやって作るのが正解?
エンディングノートを作る際は、まず「自分が何を残したいのか」を明確にすることが大切です。漠然と書き始めるのではなく、目的をはっきりさせることで、必要な情報を漏れなく整理できます。
最初に準備したいのは、氏名・生年月日・住所などの基本的なプロフィールです。これは万一のときに身元確認や連絡の起点となるため、欠かせない項目です。その後、家族構成や資産状況、保険・年金情報など、実務的な情報を段階的に記入していくのが理想です。
また、病気になったときの治療方針や延命措置への希望、葬儀やお墓のことなども、書ける範囲で明記しておくと、家族が迷わずに対応できます。特に医療や介護の希望は、意思確認が難しくなる場面で大きな手がかりになります。
一方で、エンディングノートは法的な効力を持ちません。たとえば財産分与など、法律に関わる内容は別途「遺言書」として整える必要があります。エンディングノートは、あくまでも家族や周囲の人へのメッセージや意向を伝えるためのものです。
このように、順序立てて情報を整理し、伝えたいことを明文化することが、エンディングノート作成の基本となります。
書き方のコツと押さえておきたい項目とは
エンディングノートを書くときに意識しておきたいのは、「完璧を目指さないこと」です。最初からすべてを埋めようとすると、かえって手が止まりやすくなります。大切なのは、まず書き始めてみることです。
書きやすい項目から手を付けるのが一つのコツです。たとえば、自分史や思い出深い出来事、趣味のことなど、感情が乗りやすい内容はスムーズに筆が進みます。その流れで徐々に、医療や介護、財産の話題にも取り組むとよいでしょう。
文章の形式は自由です。箇条書きでも日記のような形でも構いません。ただし、読み手が理解しやすいように、要点を短く簡潔に書くことが望ましいです。また、年月が経つにつれて情報は古くなっていくため、定期的に見直しや加筆を行うことも意識しておく必要があります。
注意点としては、情報を詰め込みすぎないことです。受け取る側が疲れてしまわないように、内容を厳選し、伝えたいメッセージを明確にすることが求められます。
押さえておきたい代表的な項目は、基本情報、家族へのメッセージ、資産・保険の記録、医療・介護の希望、葬儀・納骨に関する希望、SNSやデジタル遺品の整理などです。近年では、ペットのことを書き残す人も増えています。
一気に完成させる必要はありません。ライフスタイルの変化に合わせて少しずつ整えるつもりで、気軽に書いていくことが大切です。
エンディングノートはどこで手に入るの?購入先の選び方
エンディングノートは、思っている以上にさまざまな場所で入手できます。購入先を選ぶ際は、自分がどれだけの内容を記入したいか、どのような形式で残したいかによって選択肢が変わってきます。
一般的には、書店や文房具店で市販のエンディングノートを購入するのが手軽です。中身を確認してから選べるという安心感がありますし、種類も豊富です。また、大型書店では、医療や介護、法律の情報がまとまった専門的なノートも置かれていることがあります。
一方で、インターネット通販を利用すれば、自宅にいながら多様な種類のエンディングノートを比較検討できます。レビューを参考にしながら、自分に合いそうなものを選ぶのもひとつの方法です。ただし、実物を手に取れないため、紙の質感や書きやすさなどが分かりにくいというデメリットもあります。
無料で手に入れたい場合は、市区町村の役所や社会福祉協議会などが配布しているケースもあります。内容はやや簡易的なことが多いですが、基本を押さえるには十分です。高齢者向けのイベントやセミナーで配布されることもあります。
選ぶ際は、表紙のデザインよりも「自分が継続して書きたくなるかどうか」を重視しましょう。必要な項目が整理されているか、書き込み欄が足りているかなど、自分の用途に合った構成になっているかをチェックすることが大切です。
市販と自作、どちらの作り方がおすすめ?
エンディングノートを市販で手に入れるか、自作するかは、それぞれの目的や性格によって合う方法が異なります。どちらにも明確なメリットと注意点があります。
市販のノートは、あらかじめ書くべき項目が整っているため、何から書き始めていいか分からない人には特に向いています。用紙のデザインも工夫されており、読み手にとっても見やすく整理されています。加えて、法務や医療の視点を取り入れた構成のものもあり、内容に信頼感があります。
ただし、すでに記載する項目が決まっている分、不要なページがあったり、自分の考えを自由に記録しにくいと感じることもあります。また、紙質やフォントが好みに合わないと、続けて記入する意欲が湧かないということもあるでしょう。
一方、自作の場合は、ノートやパソコン、テンプレートなど自分の使いやすいツールを選べます。必要な項目だけを入れて自由に構成できるため、自分らしい内容に仕上げたい人にはぴったりです。表現方法や構成を柔軟に工夫できるのは大きな魅力です。
その反面、自作には手間がかかります。何を書いたらいいのか迷いやすく、必要な情報が漏れてしまうリスクもあるため、ある程度の下調べが必要になります。最初に構成を決めるのに時間がかかる点も考慮しておく必要があります。
選ぶ際は、「自分が最後まで書ける形式かどうか」を基準にするのがポイントです。完璧に作り込むよりも、まず一歩を踏み出すことのほうが大切です。
価格はいくらくらい?エンディングノートの相場を知ろう
エンディングノートの価格は、安価なものから高価格帯のものまで幅があります。選ぶノートの形式や内容、紙質によって値段は大きく異なるため、自分がどのような目的で使いたいのかをはっきりさせることが大切です。
比較的手軽なタイプであれば、数百円程度で購入できます。これは文房具店やコンビニなどで見かけるシンプルな構成のもので、最低限の情報を記入するには十分です。初めて書く人や、とりあえず形にしてみたいという場合には適しています。
一方で、1,000円以上の価格帯になると、法律や医療の知識を取り入れた構成のものや、デザイン性に優れた商品が多くなります。解説付きで分かりやすく、記入スペースもゆとりがあるため、じっくり書き込みたい方に向いています。装丁がしっかりしていて保存性が高いものも、この価格帯に多く見られます。
また、無料で入手できるエンディングノートも存在します。行政機関や地域の福祉団体が配布しているケースもあり、内容は簡易的ながら基本を押さえたものが中心です。ただし、デザインや紙の質感にはあまりこだわられていないことが多いため、見た目にこだわりたい方には不向きかもしれません。
価格だけで判断せず、自分が書き続けられる内容かどうか、読み手に伝わりやすい構成かどうかを見極めることがポイントです。
手に入る場所によって何が違う?内容と形式の違いを比較
エンディングノートは入手先によって構成や雰囲気が大きく異なります。どこで手に入れるかを選ぶことは、内容の質や書きやすさにもつながります。
書店で販売されているエンディングノートは、カテゴリ別に情報が整理されているものが多く、記入しやすいフォーマットが整っています。医療、介護、葬儀、資産など、それぞれの項目に見出しやガイドがあり、初心者でも迷わずに進められる構成が特徴です。装丁が丁寧で保存に向いている点も見逃せません。
インターネットで販売されている商品は、種類が豊富です。自分に合ったスタイルを探しやすく、レビューを参考にできるのがメリットです。ただし、実際に手に取って中身を確認できないため、思っていたものと違う印象を受けることもあります。
行政機関や地域の団体が配布するエンディングノートは、社会福祉の観点から作られているため、内容が実用的かつシンプルです。特定の年齢層や事情を想定している場合が多く、生活に即したテーマが選ばれています。ただし、デザイン性は最低限に抑えられており、個人の感情や想いを自由に書き残すには少し物足りないと感じることもあるでしょう。
前述の通り、どこで手に入れるかによって、書き手の気持ちの入りやすさや、受け取る側の理解のしやすさにも影響があります。選ぶ際には、入手先と内容のバランスを見ることが大切です。
エンディングノートの作り方と選び方のポイントを徹底解説
人気のエンディングノートはなぜ選ばれているのか
人気のあるエンディングノートには、いくつか共通する特徴があります。その一つが「使いやすさ」です。見出しや記入欄が整理されており、どこに何を書けばいいかが直感的に分かるようになっているため、書き進めるハードルが低くなっています。
また、紙質やデザインにもこだわっている商品が多く、長期間保存しても劣化しにくい点が評価されています。開きやすい製本や、ペンがにじみにくい工夫など、細かい配慮がされていることで、記入時のストレスが少ないのも理由のひとつです。
感情や想いを書けるページが多く設けられているのも、選ばれるポイントです。形式的な情報だけでなく、家族への手紙や人生の振り返りができる構成は、多くの人にとって書く意欲を高めるきっかけになります。
さらに、人気のノートは項目ごとに簡単な説明文が添えられている場合があり、何を書けばいいのかを迷わずに済みます。このような補足があることで、初めての人でも安心して取り組めるようになっています。
選ばれている背景には、「誰にとっても扱いやすい」という工夫が積み重ねられていることが大きく影響しています。
初めての人におすすめしたいエンディングノート3選
初めてエンディングノートを書く方には、複雑すぎない構成で、なおかつ必要な情報が網羅されているノートが適しています。ここでは、そうした条件を満たす3つのタイプを紹介します。
1つ目は、「シンプル構成タイプ」です。これは必要最低限の項目に絞られており、記入の負担が少ないのが特長です。たとえば、名前・連絡先・医療や介護の希望といった基本情報のみで構成されているため、書く内容に迷うことがほとんどありません。高齢の方や短時間でまとめたい人に向いています。
2つ目は、「質問形式タイプ」です。「私の大切な思い出は?」「延命治療についてどう考えているか?」など、具体的な問いかけに答えていく形式で進められるので、自然と内容が整理されていきます。書きやすさと深い思考を両立できるため、自分の気持ちを丁寧に残したい方におすすめです。
3つ目は、「家族との共有型」です。家族が読みやすいレイアウトや、メッセージ欄が多く設けられているのが特徴です。将来、家族が読むことを想定しているため、記録としてだけでなく、伝える道具としての役割も担っています。写真や手紙を差し込めるポケットがついている商品もあり、思い出と一緒に残せる点が魅力です。
初めてでも書き進めやすく、見返しても整理されていて読みやすいこと。そうした視点で選ぶと、自分に合った1冊が見つかりやすくなります。
エンディングノートはいくらからある?価格帯別の特徴
エンディングノートの価格帯は、数百円から数千円まで幅があります。安価なものと高価格帯のものでは、見た目や中身、使い心地にそれぞれ特徴があります。
500円前後で販売されているノートは、シンプルなレイアウトが中心です。必要な情報を一通り記入できる構成にはなっていますが、デザインや紙の厚みなどは控えめなものが多く、繰り返しの記入や長期保管にはやや不向きな面もあります。ただし、初めて書いてみたい人や、一度書いてみて感覚をつかみたい人には適しています。
1,000円〜1,500円程度の中価格帯になると、使いやすさを重視した仕様が増えてきます。項目の説明が丁寧に記載されていたり、書きやすい罫線やガイドが付いていたりするなど、実際に書く人の立場を意識した工夫が施されています。贈答用として選ばれることもある価格帯です。
2,000円を超える高価格帯になると、紙の質感や装丁がしっかりしていて、保存性にも優れています。読み手を意識したデザインが多く、メッセージ欄や写真の貼り付けスペースなど、記録だけでなく思いを残す工夫も目立ちます。何度も見返すことを前提とした作りになっており、大切な記録を長く残したい人には適しています。
価格が上がるほど、書き手の意図を丁寧にくみ取る設計になっていく傾向があります。どこまでの情報を残したいかを先に考えることで、自分にとって無理のない価格帯を選びやすくなります。
無料でも使える?手に入るエンディングノートの種類
無料で利用できるエンディングノートもいくつかの形で存在しています。有料の商品と比べると選択肢は限られますが、必要な情報を簡潔に整理するには十分なものもあります。
まず、自治体や福祉団体が作成・配布しているタイプがあります。これらは高齢者支援の一環として提供されるケースが多く、役所の窓口や地域包括支援センターなどで入手できることがあります。構成は基本情報、医療・介護の希望、家族への伝言など最低限に絞られており、書きやすさを重視した内容になっています。
次に、保険会社や葬儀関連の企業が提供している無料配布のノートもあります。パンフレットに近い感覚で作られており、自社サービスと連動するような構成になっている場合があるため、内容には多少の偏りが出ることもありますが、項目の確認には役立ちます。
PDF形式でダウンロードできるテンプレートも、一部の団体や企業が公開しています。自宅のプリンターで印刷すればすぐに使える手軽さがありますが、印刷する手間や用紙の管理などは自己責任になります。書き込みやすさを求めるなら、紙質にも気を配る必要があります。
無料のノートは手軽に始められる反面、デザインや構成が単調だったり、項目の深掘りができなかったりするケースもあるため、用途を明確にした上で選ぶと失敗が少なくなります。
書きやすさを重視するならどんなノートを選ぶべき?
書きやすさを重視したい場合は、自分の性格や記入の目的に合った構成のエンディングノートを選ぶことがポイントです。まず、ページのレイアウトが整っていて、どこに何を書くのかが一目でわかるものは、途中で手が止まりにくくなります。文字を詰め込まずに、余白がしっかりあるノートは、気持ちにもゆとりを持って書けるのでおすすめです。
また、項目ごとにガイド文や見本が載っているものは、何を書くか迷ったときの助けになります。たとえば「家族へのメッセージ」など感情が関わる内容でも、書き出し例があるだけで手が動きやすくなります。
紙の質も意外に大切です。書いていてペンが引っかからない、インクがにじまないなどの細かい書き心地は、地味にストレスを減らしてくれます。薄い紙は裏写りしやすいため、ある程度の厚みがある方が安心です。
さらに、記入欄の広さも見逃せません。文章をしっかり書きたい人には、余白や罫線が多めに取られているノートが適しています。逆に、箇条書きで簡潔に記録したい人には、コンパクトな構成のノートのほうが合っています。
気持ちが続かないことを想定して、途中から書き進められる構成になっているかもチェックしておくと良いです。完璧主義にならず、書けるところから気楽に始められる工夫があると、継続しやすくなります。
デジタルと紙のどちらを選ぶ?それぞれのメリットとデメリット
エンディングノートを書く方法には、紙に記入するスタイルとデジタルで作成する方法の2つがあります。それぞれに良さがあり、使う人の生活スタイルや目的によって向き不向きが異なります。
紙のノートは、手で書くことで考えを整理しやすくなり、感情も込めやすいという特長があります。ページをめくって全体像をつかめるので、家族が読み返すときにも見やすく、保存にも適しています。特に高齢の方にとっては、デジタルよりも慣れ親しんだ紙の方が取り組みやすいことが多いです。
ただし、一度書いた内容を修正するのは少し面倒です。新たに書き直す手間が発生しやすいため、こまめな見直しには向いていない面もあります。また、保管場所に気を使わないと、紛失や劣化のリスクもあります。
一方で、デジタル形式は修正や更新がしやすく、内容の追加も簡単です。クラウド保存やパスワード管理によって、紛失の心配が減るのも大きな利点です。特定の家族にしか見られないように制限できるなど、プライバシー管理がしやすい点もあります。
しかし、操作に慣れていない人にとっては、パソコンやスマートフォンの扱い自体がハードルになります。また、将来的に使えなくなるソフトやサービスのリスクもあるため、定期的にデータの確認やバックアップが必要です。
どちらを選ぶかは、「書くことが目的」なのか「残すことが目的」なのかによって変わってきます。自分が続けやすい方法を優先することが、最も重要です。
ライフストーリーを使ってあなたの人生を記録してみませんか
「ライフストーリー」とは家族や家系の記憶をあなたが次世代へ受け継ぐことができるサービスです。
遺書や遺言書とは異なる新しい形のエンディングノートです。
無料プランも用意されておりますので、まずは登録して使ってみてください!
\無料登録はコチラから/
概略:初心者でもわかるエンディングノートの作り方と選び方の基本のまとめ
