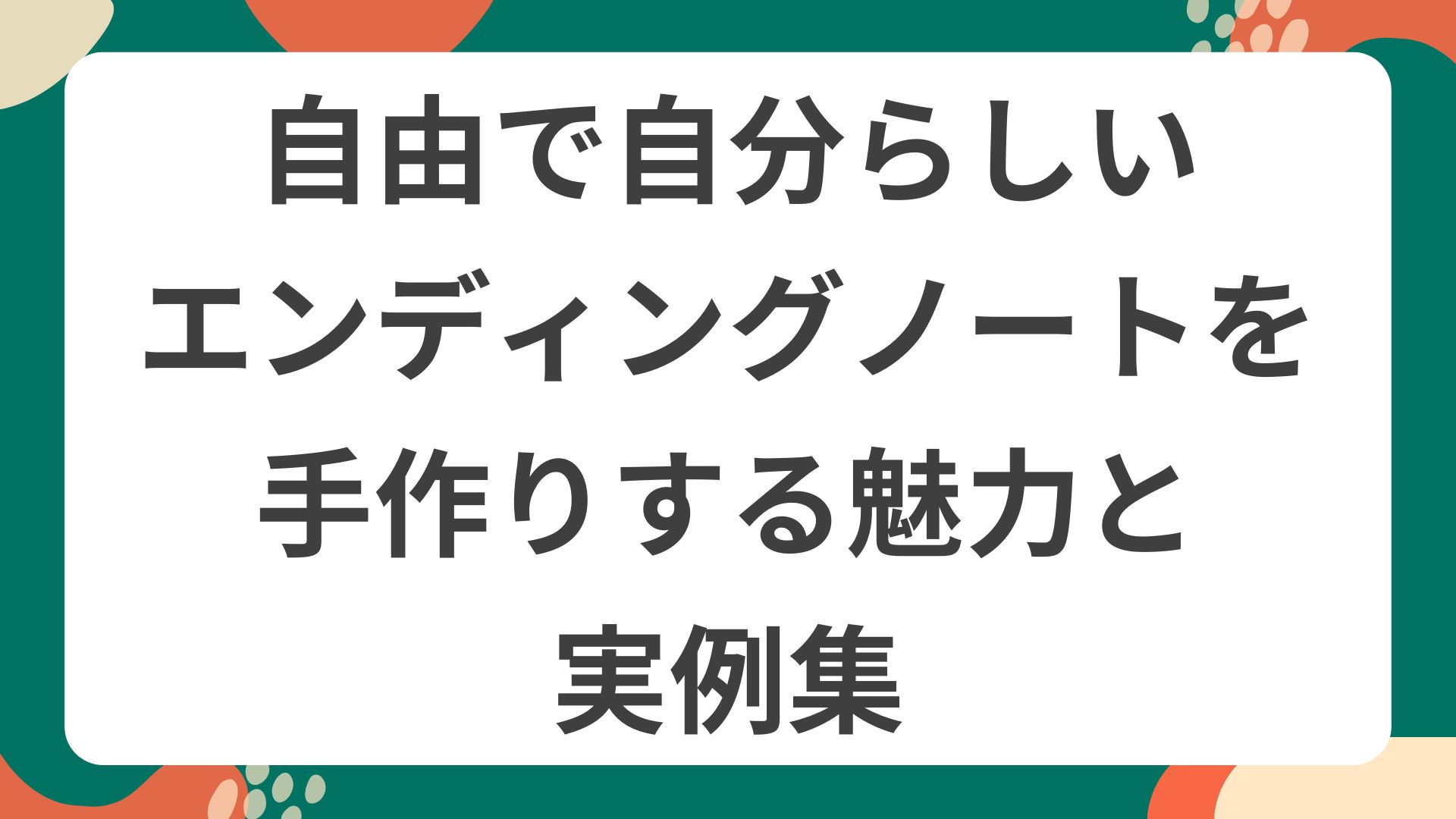
エンディングノートを手作りしようと考えている方の多くは、「自分の言葉で大切なことを残したい」と感じているのではないでしょうか。市販のノートでは伝えきれない想いや、自分に本当に必要な情報だけを記録できるのが、手作りならではの魅力です。エンディングノートを手作りすることで、形式に縛られず、自由で自分らしい一冊を作ることができます。この記事では、そんな手作りエンディングノートの基本的な作り方から、実際にどのように活用できるかといった実例まで、初心者にもわかりやすく丁寧にご紹介していきます。家族への想いを形にしたい方や、これから終活を始めたいと考えている方にとって、きっと参考になるはずです。
記事のポイント
- エンディングノートを手作りするメリットと注意点
- 手作りエンディングノートの基本的な作成手順
- 必要な道具やテンプレートの活用方法
- 市販品との違いや活用場面の具体例
エンディングノートを手作りするの魅力と基本的な作り方
エンディングノートとは何か?手作りする前に知っておきたい基礎知識
エンディングノートとは、自分の人生の記録や、万が一のときに家族へ伝えたい情報をまとめておくノートのことです。法的な効力はありませんが、介護や医療、葬儀、財産、思い出など幅広い内容を自由に記載できる点が特徴です。
書く理由は、残される家族の負担を減らすためです。例えば、延命治療に関する希望や、葬儀の形式、連絡してほしい知人のリストがあるだけでも、家族は迷わず判断できます。特に医療や介護の場面では、本人の意思が事前に伝えられているとスムーズな対応が可能になります。
一方で、エンディングノートと遺言書を混同してしまう人も少なくありません。遺言書には法的効力がありますが、エンディングノートにはその力がありません。そのため、重要な財産分与などは必ず遺言書で行い、エンディングノートには補足的な情報を記載する形が理想です。
また、内容があいまいだったり、更新されていなかったりすると、かえって混乱を招くこともあります。書くからには、内容の正確さや見直しの頻度にも気を配る必要があります。
手作りエンディングノートが選ばれる理由とは?
手作りのエンディングノートが注目されている理由のひとつは、自由度の高さにあります。市販のノートでは内容や構成があらかじめ決まっているため、自分に不要な項目も含まれてしまいます。手作りであれば、自分に必要なことだけを選び、自分の言葉で書き残すことができます。
また、コストを抑えられるのも大きなポイントです。ノートやファイル、パソコンの文書ソフトなど、身近にある道具で始められるため、わざわざ専用のノートを買う必要はありません。無料テンプレートなども活用すれば、ほぼゼロ円で作ることも可能です。
さらに、記録する過程そのものが自分の人生を見つめ直す時間になります。写真を貼ったり、イラストを描いたりしながら作成することで、形式にとらわれない温かみのあるノートに仕上げることもできるのです。
ただし、自由に作れるぶん、構成がバラバラになって読みづらくなったり、大事な情報が抜けてしまったりするリスクもあります。見やすさや整合性を保つ工夫は必要です。テンプレートを下書き代わりに活用しながら、自分らしい形にまとめていくのが良いでしょう。
簡単に始められるエンディングノートの作り方を紹介
始めに必要なのは「書きたいことを大まかに決めること」です。すべての項目を完璧に埋めようとせず、自分が今書ける範囲から始めて問題ありません。例えば「自分の基本情報」や「連絡してほしい人のリスト」など、身近な内容から手をつけると進めやすくなります。
次に用意するのはノートかファイルです。特別なものを買う必要はありません。自宅にある普通のノートやルーズリーフ、あるいはパソコンで文書を作成しても構いません。文字を書くことに抵抗があれば、箇条書きからでも十分です。
構成に迷った場合は、大まかに「個人情報」「医療・介護」「財産」「葬儀」「メッセージ」のように項目を分けてみると、全体が把握しやすくなります。ページごとに見出しを書いておくだけでも、内容の整理に役立ちます。
一方で、最初から完璧を目指すと手が止まりがちです。気軽に「あとから直せばいい」と考えることが、継続するコツです。まずは一つでも項目を書き出すこと、それが始まりになります。
無料で手に入るテンプレートやフォーマットの活用方法
無料のテンプレートは、手作りエンディングノートの強い味方です。項目の構成があらかじめ整理されているため、自分でゼロから考える負担を減らせます。特に初めてノートを作る方には、使い勝手の良いツールになります。
多くの場合、テンプレートはPDFやWord形式で提供されているため、印刷して手書きで記入することも、パソコンで入力することもできます。使いやすい形式を選べば、負担なく続けられるはずです。
ただし、注意すべき点もあります。テンプレートの中には、自分の事情に合わない内容が含まれていることもあるため、不要な項目は削除したり、逆に必要な内容を加筆したりする柔軟さが必要です。
また、複数のテンプレートを比較しながら、自分に合う構成やデザインを選ぶことも大切です。見やすさや項目の順番が合っていると、読み返すときにもストレスが少なくなります。
最初はテンプレートをなぞるようにして始めても問題ありません。慣れてきたら、自分流に書き方をアレンジすることで、より使いやすいエンディングノートに育っていきます。
手作りノートの中身をどう整理する?記入のポイントを解説
エンディングノートを手作りする場合、項目の順番や情報の分け方が非常に大切です。頭の中で内容を整理していても、実際にノートに書くとなると迷ってしまうことがあります。だからこそ、あらかじめ大きなカテゴリに分けておくと書きやすくなります。
例えば、「自分について」「医療・介護」「財産関係」「葬儀や供養」「家族や友人へのメッセージ」など、テーマごとにページを分ける方法がおすすめです。そのうえで、各ページにはタイトルを書き、空白を多めに取っておくと後から加筆しやすくなります。
記入の際は、箇条書きを意識すると見やすくなります。文章で長く書いてしまうと、自分も家族も読みづらくなりがちです。必要な情報だけを簡潔に書くよう心がけましょう。
一方で、感情や思い出を書く部分では、あえて自由に綴るページを作るのも良い方法です。事務的な情報だけでなく、自分の言葉で想いを残すことができます。
前述の通り、ノートに記載する情報が多岐にわたるため、必要な情報が埋もれないようインデックスをつけておくと便利です。付箋や色分けで目印を作るだけでも、全体の整理が格段にしやすくなります。
手作りエンディングノートのおすすめ活用例とは
手作りのエンディングノートは、単なる「終活」の道具ではなく、さまざまな場面で生かすことができます。例えば、家族との話し合いのきっかけとして使うケースがあります。ノートを見せながら、「延命治療についてどう思うか」や「自分が望む葬儀の形」などを自然に話し合える場をつくることができます。
また、医療現場で活用されることもあります。入院時や通院中、急に判断が求められる状況が起こったときに、ノートに意思が書かれていれば、医療従事者がそれをもとに対応しやすくなります。
その他、財産の情報をまとめておくことで、相続時に家族が混乱せずに済むという利点もあります。通帳や証券、保険などの情報を一覧で整理しておけば、後の手続きが非常にスムーズです。
一方で、ノートを活用するには、書きっぱなしにしないことが大切です。情報が古くなると、せっかくの内容が誤解を招いてしまうことがあります。数ヶ月に一度は見直して、必要に応じて修正することを忘れないようにしましょう。
さらに、旅行や帰省の際にノートを持参し、親しい人と一緒に内容を確認するという使い方もあります。特別な機会を通じて、ノートが自然と会話のきっかけになることもあります。
エンディングノートを手作りするために必要な準備と費用の目安
エンディングノートを手作りする具体的な方法と手順
まずは、何を伝えたいかを大まかに整理してからスタートしましょう。内容がはっきりしていると、全体の流れも作りやすくなります。項目の例としては、プロフィール、医療に関する希望、財産の情報、家族へのメッセージなどが挙げられます。
次に、ノートの形式を決めます。リングノートやルーズリーフ、バインダーなど自由に選べます。書き直しや加筆のしやすさを重視するなら、差し替え可能なタイプが便利です。
ページの順番は、読みやすさを意識して構成しましょう。例えば、最初に基本情報を記入し、次に医療・介護、財産、葬儀、最後にメッセージといったように、流れを意識して組み立てると良いです。
書き始めるときは、いきなり全部書こうとせず、1項目ずつ丁寧に進めることがポイントです。負担に感じると続かなくなるので、数日に分けて作業するのがおすすめです。
誤字が気になる場合は、下書きをしてから清書する方法もあります。また、完成後も定期的に見直すことを前提に、日付を記録しておくと更新の目安になります。
手作りに必要なアイテムはどこで揃えるのがベスト?
エンディングノートを手作りするには、特別な道具は必要ありません。ただ、作業をスムーズに進めるためには、いくつかのアイテムを揃えておくと便利です。
基本的な道具としては、ノートまたはルーズリーフ、書きやすいペン、定規、付箋などがあります。これらは文房具店や100円ショップで手軽に購入できます。ルーズリーフやバインダータイプを使う場合は、穴あけパンチもあると整理がしやすくなります。
色分けをしたい場合には、カラーペンやシールも活躍します。重要な部分に目印をつけたり、自分らしいデザインにすることができるため、作る過程も楽しめるようになります。
一方で、パソコンを使って作成したい人は、WordやExcelなどのソフトを使うと柔軟に編集できます。文書作成ソフトはすでにインストールされていることが多く、追加費用がかからない場合もあります。
購入先としては、文具店が品ぞろえ豊富ですが、近所のスーパーやホームセンターでも必要なものは一通り揃います。できるだけ出費を抑えたい場合は、家にある未使用のノートを活用するのも一つの方法です。
手作りエンディングノートの価格はどれくらいかかる?
手作りでエンディングノートを作る場合、費用はほとんどかけずに済ませることも可能です。基本的な道具としてはノートやバインダー、筆記用具、場合によっては付箋やインデックス程度なので、すべて100円ショップで揃えれば500円以内で収まることもあります。
見た目にこだわりたい場合は、少し質の良いノートやファイルを選ぶと1,000円〜2,000円程度になることもあります。デザインや紙の質にこだわりがある人は文具専門店を利用するケースもあるため、その場合はもう少し高くつくかもしれません。
一方で、パソコンを使って作成・印刷する場合でも、すでにプリンターや用紙がある家庭であれば追加のコストはかかりません。ただし、インク代や用紙の質にこだわると印刷費が数百円程度はかかります。
作る目的や使い方によって、費用の幅はありますが、工夫次第でとても安価に済ませることができるのが手作りの強みです。
エンディングノートを手作りする場合、いくら用意すれば安心?
予算を決めるときは、用途と目的を考えることが大切です。とりあえず最低限の準備だけで作るのであれば、1,000円未満でも十分です。ノートとペンだけでも始められますし、気負わず書き始めたい方にはこれで十分対応できます。
一方で、ノートを長く使いたいとか、きれいに保存したいと考える場合は、2,000円から3,000円程度の余裕を見ておくと安心です。バインダー式のファイルやリフィル、見出し付きの仕切り、ラベルなどを組み合わせれば、見た目にも整理された一冊が作れます。
プレゼントとして家族に渡す予定がある場合は、さらに装飾や製本にも費用がかかることがあります。このようなケースでは、5,000円前後を目安にすると素材の選択肢も広がります。
予算を大きくかける必要はありませんが、自分がどの程度まで丁寧に作り込みたいかをあらかじめ考えておくことで、無駄な出費を避けながら満足のいくノートが完成します。
おすすめのデザインやレイアウトで見やすさをアップ
手作りのエンディングノートをより使いやすくするためには、見た目の工夫が欠かせません。たとえ内容がしっかり書かれていても、読み手がパッと見て理解できなければ意味が薄れてしまいます。
レイアウトの基本として、ページごとに見出しを設けることはとても有効です。大きめの文字で項目名を書くだけで、どこに何が書いてあるのかすぐに把握できるようになります。また、必要に応じて枠や表を使うことで、情報を整理しやすくなります。
色分けも視認性を高める方法のひとつです。例えば、医療に関する内容は青、財産情報は緑、メッセージはピンクなど、テーマごとに色を使い分けると、内容が直感的に伝わります。ただし、使い過ぎると逆にごちゃごちゃしてしまうので、色は3色程度に絞るとバランスが取れます。
さらに、メモ欄や自由記入スペースを設けておくと、あとから書き加えたいときに便利です。すべてのページをびっしり埋める必要はありません。余白を適度に残すことが、読み手へのやさしさにもつながります。
手作りと市販エンディングノートの違いを徹底比較
市販のエンディングノートは、あらかじめ項目が整っており、すぐに記入を始められるという利点があります。デザインもプロの手によって見やすく設計されており、完成された印象を与えるものが多くあります。特に終活を意識した書店のコーナーには、多様な種類が並んでいるため、自分に合う一冊を選ぶこともできます。
一方、手作りノートは自由度が圧倒的に高く、自分のライフスタイルに合わせて内容をカスタマイズできます。不要な項目を省いたり、特定の内容を詳しく書いたりと、柔軟に対応できるのが最大の特徴です。自分の手で作るからこそ、よりパーソナルで温かみのある仕上がりになります。
ただし、市販品は構成がしっかりしている分、内容が固定されていることが多く、書きたいことが書けないと感じる場面もあります。一方で手作りは、構成をすべて自分で考える必要があり、準備に時間がかかることがあります。
どちらにも良さがありますが、記録したい内容が明確で、自分のペースで作りたい人には手作りが向いています。一方で、何から書けばいいのかわからないという方には、市販のテンプレートが安心感を与えてくれるかもしれません。
ライフストーリーを使ってあなたの人生を記録してみませんか
「ライフストーリー」とは家族や家系の記憶をあなたが次世代へ受け継ぐことができるサービスです。
遺書や遺言書とは異なる新しい形のエンディングノートです。
無料プランも用意されておりますので、まずは登録して使ってみてください!
\無料登録はコチラから/
