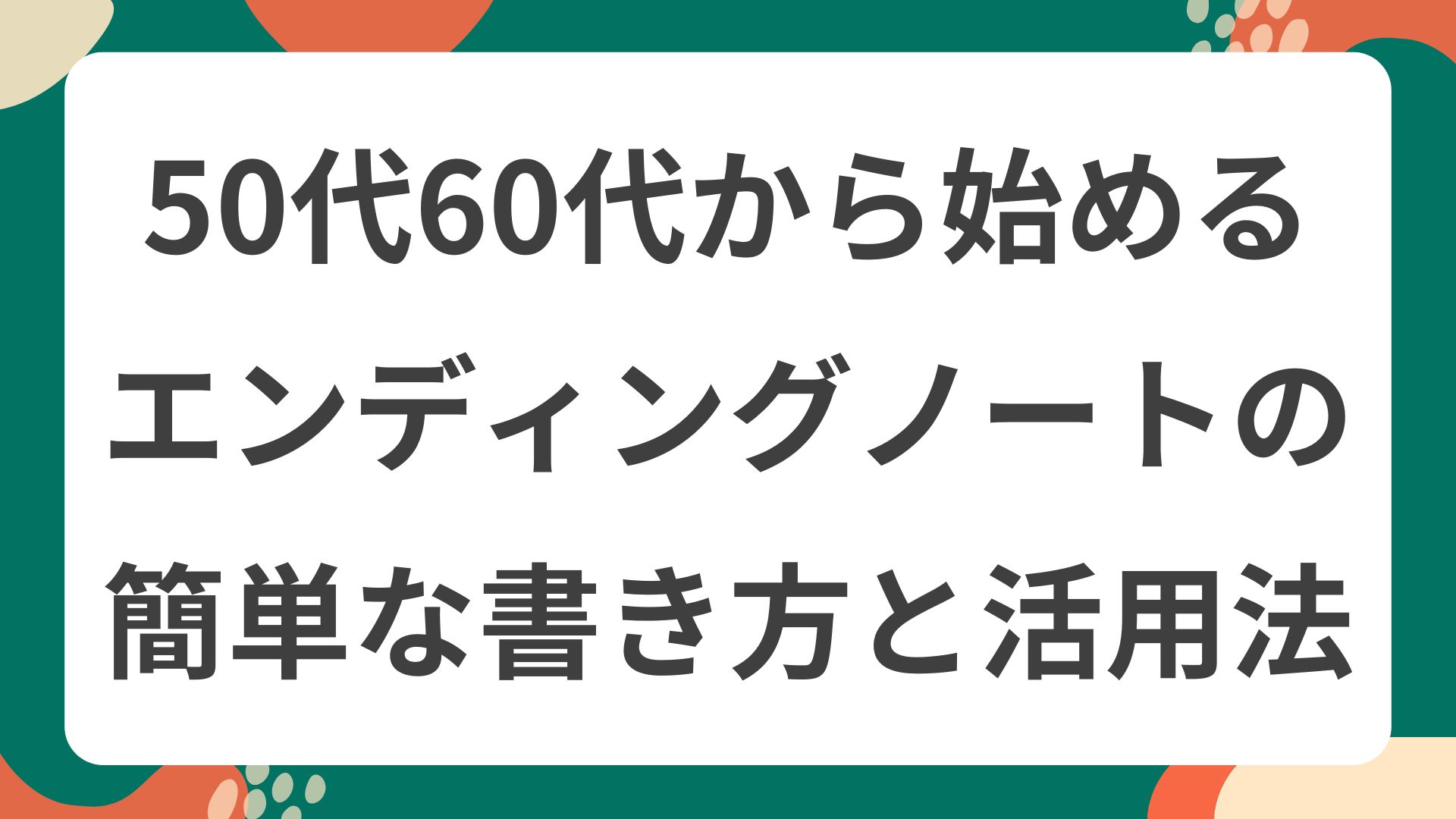
エンディングノートを書こうと思っても、「何から始めればいいのか分からない」と感じていませんか。特に50代や60代は、親の介護や相続の経験を通じて、自分自身の将来について考える機会が増える年代です。そんな今こそ、エンディングノートの書き方を学び、人生の整理や想いの伝え方を見直す良いタイミングです。
この記事では、初めての方でも安心して始められるエンディングノートの簡単な書き方をはじめ、年齢に応じた記入ポイントや活用の仕方まで丁寧に解説します。自分らしい形で準備を進めたい方、家族に負担をかけたくないと考える方にとって、きっと役立つ情報が見つかるはずです。
記事のポイント
- エンディングノートの基本的な書き方と構成
- 書き始める適切なタイミングと進め方
- 年代別に押さえておきたい記入ポイント
- 市販・無料・手作りなど各種ノートの選び方
初めてでもわかるエンディングノートの書き方をやさしく解説
エンディングノートの書き方の基本と書き始めるタイミング
まず初めに、エンディングノートは自由に書いてよいものですが、基本的な構成を押さえておくとスムーズに書き進められます。エンディングノートの基本構成には、「自分のプロフィール」「家族や親しい人へのメッセージ」「財産や保険の情報」「医療や介護に関する希望」「葬儀やお墓の希望」「デジタル遺品の管理」などが含まれます。書き方に正解はありませんが、項目ごとに分けて記入することで、読みやすく、必要な情報が明確になります。
次に、書き始めるタイミングについてですが、理想的なのは“何も困っていないとき”です。体調を崩してから慌てて書こうとすると、気力や集中力が続かず、十分な内容を残せないことがあります。特に自分の希望や価値観を冷静に整理するためには、心身ともに元気なうちに取りかかるのが望ましいでしょう。
例えば、「延命治療を望まない」といった意思がある場合、それを文章にしておくだけで、家族が迷うことなく決断できます。また、普段は照れくさくて伝えられない感謝の気持ちなども、エンディングノートに書いておくことで、思いがきちんと届く手段になります。
注意点として、エンディングノートは法的な効力を持たないという点があります。遺言書とは違い、書いた内容が必ずしも実行されるとは限らないため、大切なことは家族とも共有しておくことが大切です。
50代から始めるエンディングノートの賢い準備法
50代は仕事や家庭がある程度落ち着き、自分自身の人生を振り返る余裕が生まれる時期でもあります。このタイミングでエンディングノートを準備しておくことで、将来の備えをより丁寧に進めることができます。
なぜ50代が適しているかというと、多くの人がこの年代で親の介護や相続に直面し、「自分も準備しておかないと」と感じるからです。エンディングノートを書き始めることで、必要な情報を整理しながら、今後の生活設計も見直すきっかけになります。
例えば、まだ現役で収入があるうちに保険の見直しや、財産の整理を進めておくことができます。また、親の介護経験がある方であれば、「自分のときはこうしてほしい」という希望も書きやすくなるでしょう。
一方で、将来が見えにくいからこそ、全てを具体的に決められない場合もあります。その場合は、今わかっている部分だけでも書いておくことが重要です。情報は後からいくらでも更新できます。完璧を目指すのではなく、まずは書き出すことを意識しましょう。
そしてもう一つは、家族に自分の考えを伝えておくことです。エンディングノートにどんな意図で何を書いたのかを話すことで、誤解や不安を減らすことができます。50代のうちに準備を始めておけば、万が一のときにも慌てず対応できる土台を築けるのです。
60代が書いておきたいエンディングノートのポイント
60代になると、健康や暮らしに関する考え方が以前とは少しずつ変わってきます。だからこそ、この年代でエンディングノートに向き合うことには意味があります。特に意識したいのは、「医療の希望」「財産の整理」「介護の希望」の3点です。
まず、医療について。病気やけがで自分の意思が伝えられなくなった場合、どこまで治療してほしいのか、延命処置は希望するのか、といった考えを事前に記しておくと、家族の負担が大きく減ります。話しにくい内容ではありますが、ノートに書いておくだけで安心感が違います。
次に財産の整理です。相続トラブルを避けるためにも、自分の資産状況を明確にしておくことは大切です。預金や保険、不動産の情報を一か所にまとめるだけでも、家族が状況を把握しやすくなります。
そして介護の希望です。誰に世話をお願いしたいか、どんな施設を考えているのかなど、自分なりの方針を伝えておけば、突然の入院や介護が必要になったときも、周囲が戸惑わずに済みます。
ただし、すべてを一度に決めようとすると負担になります。思いついたことから少しずつ書き加えるという姿勢で十分です。完璧を求めず、まずは一歩を踏み出すことが大切です。
初心者におすすめのエンディングノート講座とは
エンディングノートに興味はあっても、いざ書こうとすると「何から始めればいいのか分からない」と感じる方も多いものです。そうした初心者にとって心強いのが、専門的な講座の存在です。講座では、ノートの使い方だけでなく、書く際の考え方まで丁寧に教えてくれます。
特におすすめなのは、実際に書きながら進めていくワークショップ形式の講座です。一人では進まなかった人でも、講師のアドバイスを受けながら周囲と意見を交わすことで、スムーズに記入を始められるようになります。
また、講座の内容は幅広く、医療や介護、相続、葬儀のことなど、複数の専門分野が関わってきます。講座によっては、各分野の専門家が登壇し、最新の知識をわかりやすく解説してくれることもあります。
ただし、受講料には幅があり、無料のものから数千円の有料講座までさまざまです。価格だけで判断せず、講座の目的や講師の実績を確認した上で選ぶのが良いでしょう。
さらに、最近ではオンライン講座も増えています。自宅にいながら受講できるため、外出が難しい方にも向いています。まずは気軽に参加できる講座から体験してみるのも一つの方法です。
いま人気のエンディングノートはどんな内容?
最近注目を集めているエンディングノートには、単なる記録だけでなく、「想いを伝える」工夫が施された内容が多く見られます。これまでのように資産情報や医療方針を書くだけでなく、人生の歩みや家族への感謝の言葉を自由に記せるページが増えているのが特徴です。
たとえば、幼少期の思い出や印象に残っている出来事、家族との写真を貼るスペースなどがあるノートでは、自分史のような感覚で自然とペンを動かすことができます。形式ばったものではなく、書くことを楽しめる構成になっているものが選ばれている傾向です。
また、記入例やガイドが各ページに記されているノートも人気があります。何を書けばよいか迷いがちな人にとっては、空白のページよりも「ここにはこういうことを書いてみましょう」とヒントがある方が安心です。質問形式で答えていくスタイルも、会話するように気軽に進められるため好まれています。
一方で、内容が豊富すぎるノートは途中で手が止まってしまうケースもあります。多くのページがあることがかえってプレッシャーになることもあるため、自分に合った分量やデザインを選ぶことが大切です。人気のノートが必ずしも全員に最適とは限らないという視点も忘れないようにしましょう。
エンディングノートはどこで買えるのかを詳しく紹介
エンディングノートは、意外と身近な場所で手に入ります。文具店や大型書店では、専用のコーナーが設けられていることもあり、実際に手に取って中身を確認することができます。表紙のデザインや中身の構成を直接見て選びたい方には、この方法が向いています。
一方で、最近ではインターネット通販の利用も増えています。書店のオンラインショップや大手通販サイトでは、種類も豊富でレビューも参考になるため、比較しながら選びたい人に適しています。配送までの時間が気になる場合は、事前に在庫状況を確認しておくと安心です。
また、市区町村が配布している無料のエンディングノートも存在します。配布場所は役所の福祉課や地域包括支援センターなどで、配布を行っている自治体であれば誰でも手に入れられることがあります。内容も公的支援や相談窓口の案内が載っているため、高齢者や家族にとって実用性が高いケースもあります。
ただし、無料版はデザインがシンプルで書き込み欄も限られている場合があります。情報量を整理したい人や、自分らしさを大切にしたい人には市販のノートの方が向いていることもあります。自分の目的に合った入手方法を考えることが大切です。
失敗しないエンディングノートの書き方と選び方のコツ
エンディングノートのおすすめの書き方と活用法
書き始めるときは、「絶対に完璧にしよう」と思わないことがポイントです。すべてを一度で仕上げる必要はなく、思いついた内容から順に書き込んでいく形で十分です。負担を感じずに取り組むには、ざっくりと章ごとに分けて書いていく方法が向いています。
例えば、まずはプロフィールや家族構成といった基本情報から書き始めると、比較的取り組みやすく感じます。次に、医療・介護の希望や財産に関する内容など、考える時間が必要な項目へ進んでいくとよいでしょう。順番にこだわらず、自分の中で書ける部分を優先することで、途中で手が止まるのを防げます。
書くときの形式については、箇条書きを活用すると情報が整理しやすくなります。長い文章でまとめようとすると難しく感じるかもしれませんが、短いメモのように記すだけでも十分役に立ちます。とくに、連絡先や口座情報などは簡潔にまとめることが大切です。
また、エンディングノートは書いて終わりではありません。定期的に見直すことで、状況の変化に合わせた更新ができます。ライフスタイルや価値観が変わることは誰にでもあるので、年に一度程度、目を通す習慣をつけるのが理想です。
自分に合った方法で無理なく進めるエンディングノート作成
エンディングノートの作成には、決まったスタイルはありません。紙のノートに手書きする方法が一般的ではあるものの、自分に合わなければ続けにくくなってしまいます。書きやすさや見やすさを優先して、自由に形式を選んで構いません。
たとえば、字を書くのが負担に感じる場合は、パソコンやスマートフォンを使ってデジタルで管理するという方法もあります。エクセルやワードでテンプレートを作成したり、メモアプリに必要な情報を分けて保存したりといった手段も有効です。
また、全ページを自分ひとりで完成させる必要もありません。家族と相談しながら一緒に書き進めたり、一部を信頼できる人に託したりすることで、精神的なハードルがぐっと下がります。自分ひとりで抱えこまず、周囲の協力を得る姿勢も大切です。
ただし、方法が自由とはいえ、書く内容がバラバラになってしまうと、かえって分かりにくくなります。項目ごとにページを分ける、重要な部分は目立つようにマークをつける、といった整理の工夫は必要です。
無理なく続けるには、自分の生活リズムの中に「少しずつ書く時間」を組み込むことです。たとえば、月の初めに1項目ずつ記入するなど、習慣化すれば気づけば自然に仕上がっていきます。
エンディングノートの価格はいくらが相場?無料との違いも解説
市販されているエンディングノートの価格帯は、おおむね500円から2,000円程度が多く見られます。紙質やデザイン、内容のボリュームによって差が出るため、同じエンディングノートでも仕様によって値段は大きく異なります。特にカラー印刷でイラストや記入例が豊富に載っているものは高めの傾向があります。
一方、無料で配布されているエンディングノートも存在します。地方自治体や保険会社、介護施設などが作成したものは、生活支援の一環として無償で提供されていることがあります。実用性は十分ありますが、内容が簡易的であったり、広告が入っていたりすることもあります。
例えば、市販のノートには、自分史を記す欄や写真スペース、終末医療に関する詳しい説明が掲載されている場合があります。対して無料のものは、最低限の項目に絞られており、余白も少なめなことが多いです。そのため、より自由に記録したい人や情報を丁寧に整理したい人には、有料版の方が扱いやすいと感じるかもしれません。
ただし、無料だから劣っているということではありません。内容が明確で、必要最低限の項目だけでよいという方には、十分に役立つ道具になります。予算を気にせず、まずは気軽に試したい場合には、無料版を使ってみるのも良い方法です。
エンディングノートはどこで手に入る?入手先を比較
エンディングノートを手に入れようとしたとき、いくつかの選択肢があります。まず、最も一般的なのが書店です。大きな書店では専用コーナーが設けられていることもあり、実物を手に取って中身を確認しながら選べます。中身の構成や文字の大きさなど、自分に合ったものを選びたい方にとっては安心できる方法です。
次に、インターネット通販です。自宅にいながら注文でき、種類も豊富にそろっているのが特徴です。レビューを確認しながら比較検討できるため、選びやすいと感じる方も多いでしょう。ただ、実物を見られない分、到着後に「思ったより書きにくい」と感じることもあるかもしれません。
他には、銀行や保険会社が顧客向けに配布しているケースもあります。サービスの一環として提供されることがあり、使いやすいフォーマットであることが多いです。条件付きで配布されている場合もあるため、事前の確認は必要になります。
そしてもう一つ、自治体による無料配布も見逃せません。地域の高齢者支援サービスの一部として、役所の窓口や地域のイベントなどで手に入ることがあります。必要な情報が簡潔にまとまっており、初めての人でも取り組みやすい構成になっていることが多いです。
どこで手に入れるかは、自分の使い方や目的によって選ぶのがポイントです。手軽さを優先するのか、内容の充実度を重視するのかによって、最適な入手先は変わってきます。
書き方を学ぶなら講座と独学どちらがいい?それぞれの特徴
書き方をしっかり身につけたいと考えたとき、多くの人が「講座を受けるべきか、それとも自分で進めるべきか」で迷います。どちらにも向き不向きがあり、自分の性格や目的に合った方法を選ぶことが大切です。
まず、講座に参加するメリットは「専門的な知識をわかりやすく学べること」です。講師が一から丁寧に教えてくれるので、内容を誤解せずに書き進められます。特に、医療や相続といった専門性の高い項目は、解説を受けながら理解を深められる点が安心です。また、同じ目的を持った参加者と交流できるのも講座ならではの魅力です。
一方で、時間や費用に余裕がない場合には、独学の方が柔軟です。市販のエンディングノートや解説書を参考に、自分のペースで取り組めるので、忙しい人にも向いています。ただし、項目の意図が分かりづらかったり、書くべきことに迷ったりすることもあり、途中で止まってしまう可能性もあります。
講座に向いているのは、誰かのサポートがあった方が取り組みやすい人や、正確な知識をきちんと得たい人。逆に、考える時間を自由に確保したい方や、すでにある程度知識がある方は独学での作成も十分可能です。
市販と手作りのエンディングノートはどちらがおすすめか?
エンディングノートには、市販の完成されたノートを使う方法と、自分で一から手作りする方法の2つがあります。それぞれに利点と課題があるため、選び方は「自分にとって何が書きやすいか」が鍵になります。
市販のエンディングノートは、構成や項目がすでに整っており、迷わず書き進めやすいのが特徴です。特に初めての方には便利で、書く順番や内容の見本があることで、取り組みやすくなります。さらに、法的な視点や実務的な内容が盛り込まれているものもあり、実用性を重視する方には向いています。
一方、手作りのノートは自由度が高く、自分の言葉や想いを好きなように書けるのが魅力です。書く内容に決まりがないため、形式にとらわれずにページを構成したい人や、趣味や人生観をしっかり残したい人にはぴったりです。ノートのデザインやレイアウトにこだわることもでき、自分らしい一冊を作ることができます。
ただし、手作りは自由な反面、何をどこに書くかを自分で決めなければならず、整理が難しいという面もあります。また、重要な情報が漏れてしまうリスクもあるため、必要な項目をリスト化するなどの工夫が求められます。
形式よりも、自分が「これなら書き続けられる」と感じる方法を選ぶことが、無理のないエンディングノート作成の第一歩になります。
ライフストーリーを使ってあなたの人生を記録してみませんか
「ライフストーリー」とは家族や家系の記憶をあなたが次世代へ受け継ぐことができるサービスです。
遺書や遺言書とは異なる新しい形のエンディングノートです。
無料プランも用意されておりますので、まずは登録して使ってみてください!
\無料登録はコチラから/
概略:50代60代から始めるエンディングノートの簡単な書き方と活用法のまとめ
