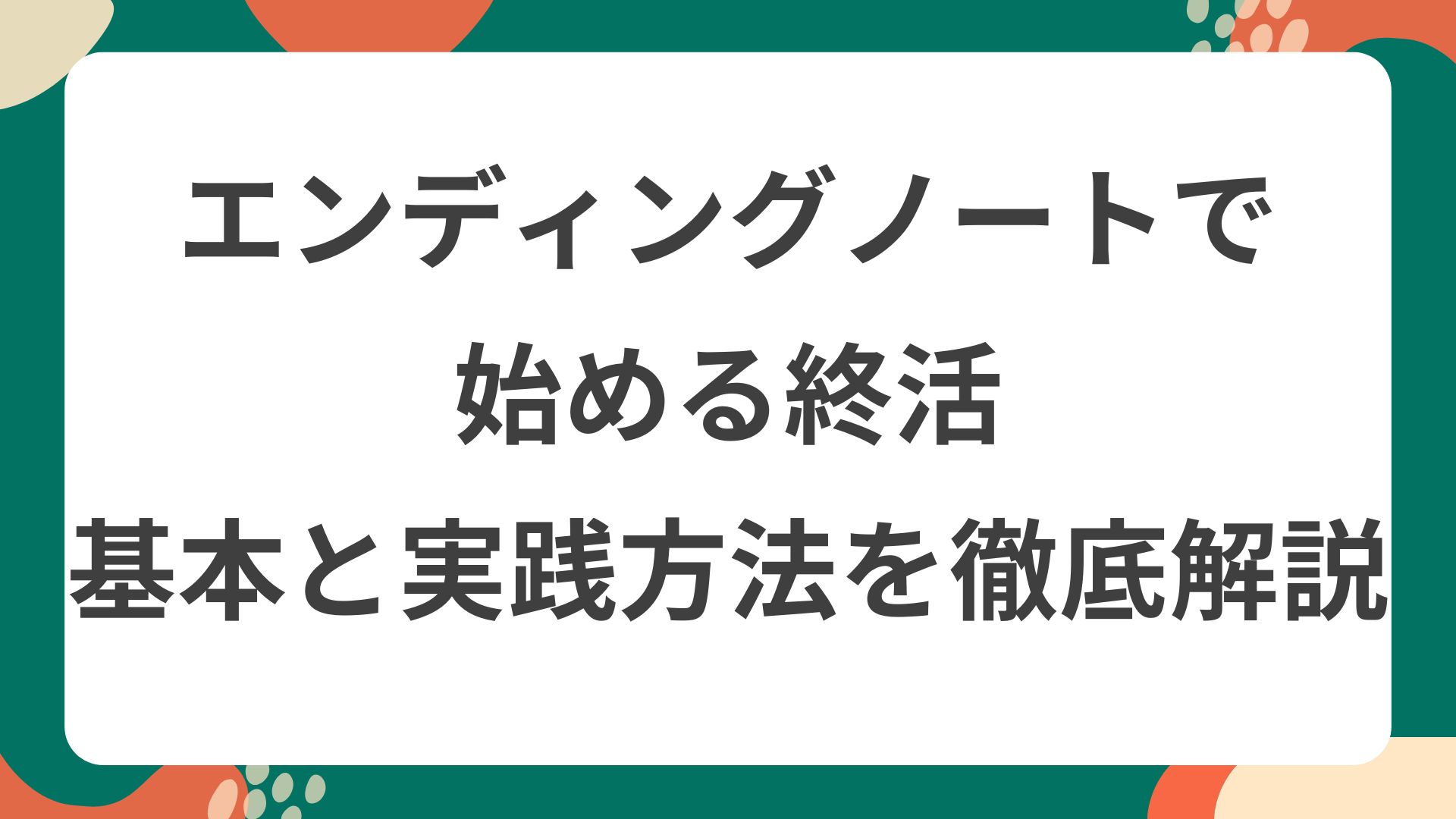
終活の一環としてエンディングノートに関心をお持ちの方も多いのではないでしょうか。エンディングノートは、ご自身の想いや情報を残すための大切なツールです。しかし、いざ書こうとすると、終活のエンディングノートにはどんな内容を書けばいいですか、エンディングノートに最低限書くべきことは何だろう、エンディングノートは遺言書になるかといった疑問や、エンディングノートの完成率はどの程度なのかという不安も出てくるかもしれません。また、どこで手に入るのか、例えば市役所で無料の見本はあるのか、ダイソーのような身近な場所でも購入できるのか、あるいは無料ダウンロードできるExcel形式の無料でシンプルなテンプレートはあるのか、そして若い人向けのおすすめのノートはあるのかなど、具体的な情報を知りたい方もいらっしゃるでしょう。この記事では、これらの疑問にお答えし、エンディングノート作成の一歩をサポートします。
この記事を読むことで、あなたは以下の点を理解できます。
記事のポイント
- エンディングノートの基本的な役割と遺言書との違い
- エンディングノートに記載すべき具体的な内容とそのポイント
- エンディングノートの様々な入手方法と選び方のヒント
- エンディングノートをスムーズに作成するためのコツ
エンディングノートで始める終活の基本
エンディングノートについて理解を深めるために、まずは基本的な情報から押さえていきましょう。ここでは、エンディングノートに何を書くのか、遺言書との違い、最低限必要な項目、完成率、そして若い世代にとっての意義について解説します。
終活ノートに書くべき内容は?
終活で用いるエンディングノートには、ご自身の情報や意思を正確に伝えるために、様々な項目を記載できます。まず、ご自身の基本情報として氏名、生年月日、現住所、本籍地、血液型などを記録します。これらは、万が一の際に必要な手続きで役立ちます。
次に、資産や財産に関する情報です。預貯金口座、不動産、有価証券、加入している生命保険(保険会社名、受取人など)、年金の種類や番号などを整理して記載します。これにより、残された家族が財産状況を把握しやすくなります。
また、医療や介護に関する希望も大切な項目です。持病やかかりつけ医、アレルギー情報、常用薬、延命治療の希望の有無、希望する介護の形や施設などを具体的に記しておけば、ご自身の判断能力が低下した際にも意思を尊重してもらいやすくなります。
さらに、葬儀やお墓に関する希望も詳細に書き留めておくとよいでしょう。希望する葬儀の形式(家族葬、一般葬など)、宗教や宗派、菩提寺の有無、遺影に使ってほしい写真、お墓の場所や種類、納骨方法などを記載します。誰に訃報を伝えてほしいかの連絡先リストも作成しておくと、遺族の負担を軽減できます。
ペットを飼っている場合は、ペットの名前、年齢、種類、性格、好きな食べ物、かかりつけの動物病院、そして自分の死後に世話をお願いしたい人や団体についても明記しておくことが望ましいです。
そして、家族や友人へのメッセージもエンディングノートならではの項目です。普段はなかなか伝えられない感謝の気持ちや思い出、伝えたい言葉などを自由に綴ることができます。
これらの項目以外にも、趣味や特技、大切な思い出、自分の人生観、デジタル遺品(SNSアカウントやオンラインサービスのID・パスワードなど)の取り扱いに関する希望なども記載することが可能です。エンディングノートは自由な形式で作成できるため、ご自身にとって必要な情報を整理し、残された方々への思いやりを形にすることが肝要です。
エンディングノートと遺言書の違い
エンディングノートと遺言書は、どちらも終活に関連して作成されるものですが、その性質や役割には明確な違いがあります。これらの違いを理解しておくことは、ご自身の意思を適切に残すために非常に大切です。
最も大きな違いは、法的効力の有無です。遺言書は、民法に定められた方式に従って作成された場合に限り、財産の相続や身分関係(子の認知など)に関して法的な拘束力を持ちます。これに対して、エンディングノートには法的な効力は一切ありません。たとえエンディングノートに財産の分け方について記載したとしても、それはあくまで希望を表明するものであり、法的に相続人を拘束するものではないのです。
作成の形式についても異なります。遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といったように、法律で厳格な形式が定められており、この形式を満たさないものは無効となります。一方、エンディングノートには決まった形式はなく、市販のノートや大学ノート、デジタルデータなど、どのような形でも自由に作成できます。
記載できる内容の範囲も異なります。遺言書に記載できる事項は、主に財産分与や相続人の指定など、法律で定められたことに限定されます。これに対し、エンディングノートは記載内容に制限がなく、前述の通り、自身の基本情報、医療や介護の希望、葬儀の希望、家族へのメッセージなど、あらゆる事柄を自由に書き記すことが可能です。
作成費用や内容の確認時期にも違いが見られます。エンディングノートは数百円程度の市販ノートから作成でき、いつでも内容を確認したり書き直したりできます。対して遺言書、特に公正証書遺言を作成する場合は数万円以上の費用がかかることがあり、その内容は原則として本人の死後に確認されることになります。
これらの点をまとめた表を以下に示します。
このように、エンディングノートは遺言書よりも気軽に、そして広範囲な事柄について自分の考えや希望をまとめることができるツールと言えます。ただし、財産に関する法的な意思表示は遺言書で行う必要がある点を忘れないようにしましょう。
最低限書くべきこととは?
エンディングノートに何をどこまで書くかは個人の自由ですが、いざという時に家族が困らないため、またご自身の意思を確実に伝えるために、最低限記載しておきたい項目がいくつかあります。これらを整理しておくことで、エンディングノートの役割をより効果的に果たせるでしょう。
まず、ご自身の正確な個人情報は不可欠です。氏名、生年月日、現住所、本籍地は、各種手続きの基本となります。また、運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードといった身分証明書の保管場所も明記しておくと、家族がスムーズに対応できます。
次に、医療や介護に関する明確な意思表示です。アレルギーの有無、持病、常用している薬、かかりつけの病院といった医療情報は、緊急時に医療関係者が迅速かつ適切な処置を行う上で助けになります。加えて、延命治療を希望するかどうか、どのような介護を望むか、希望する施設があるかなど、ご自身の判断能力が低下した場合に備えた意思を具体的に示しておくことは、家族の精神的負担を軽減し、ご自身の尊厳を守ることにも繋がります。
そして、資産と負債の概要も把握できるようにしておくことが望ましいです。全ての詳細を記載する必要はありませんが、どのような種類の預貯金口座があるか(銀行名、支店名程度)、不動産を所有しているか、加入している生命保険の有無と保険会社名、借入金がある場合はその概要などを記しておけば、相続手続きの初動がスムーズになります。通帳や印鑑、権利証などの保管場所も併せて記載しておくと、より親切です。
葬儀やお墓に関する基本的な希望も、伝えておきたい大切な事柄の一つです。どのような形式の葬儀を望むか(例:家族だけで静かに行いたい、特定の宗教儀礼に沿ってほしいなど)、遺影に使ってほしい写真、連絡してほしい人のリストなどを残しておけば、遺族が故人の意向に沿った形で送り出すことができます。
これらの項目は、万が一の事態が発生した際に、残された家族が直面するであろう様々な手続きや判断の手助けとなる情報です。全てを完璧に書こうと気負う必要はありませんが、これらの点を意識して少しずつ書き進めることをお勧めします。
エンディングノートの完成率とは
エンディングノートを書き始める方は増えていますが、「実際に最後まで書き上げられる人の割合、つまり完成率はどの程度なのだろうか」と気になる方もいらっしゃるかもしれません。
正確な統計データとしてエンディングノートの完成率が公表されているわけではありませんが、一般的には、最後まで全ての項目を完璧に埋めて完成させる人は、必ずしも多くはないという見方があります。途中で筆が止まってしまったり、一部の項目だけを記入してそのままになってしまったりするケースも少なくないようです。
この背景にはいくつかの理由が考えられます。一つは、エンディングノートに記載する項目が多岐にわたることです。自分の情報から財産、医療、葬儀、家族へのメッセージまで、考えるべきことや調べるべきことが多く、時間と労力がかかるため、途中で負担を感じてしまうことがあります。
また、内容によっては心理的なハードルを感じることもあります。例えば、自分の死後のことを具体的に考えたり、財産について詳細に記載したりすることに抵抗を感じる人もいるでしょう。特に、普段あまり意識していない事柄について深く考える必要があるため、精神的なエネルギーを要します。
しかし、エンディングノートは一度で完璧に仕上げる必要はありません。むしろ、少しずつ時間をかけて、書けるところから書き進めていくことが大切です。例えば、まずは自分の基本情報や趣味など、気軽に書ける項目から始めてみるのがよいでしょう。気持ちの変化や状況の変化に合わせて、後から何度でも書き加えたり修正したりできるのがエンディングノートの利点です。
完成させるためのコツとしては、目的を明確に持つこと、家族と相談しながら書くこと、定期的に見直す習慣をつけることなどが挙げられます。市販のエンディングノートには、書き進めやすいように工夫されたものや、解説付きのものもありますので、そういったものを活用するのも一つの方法です。
エンディングノートの完成率という数字に一喜一憂するよりも、ご自身のペースで、ご自身の想いを整理し、残していくというプロセスそのものに意義があると考え、気負わずに取り組むことが、結果としてより充実した内容のエンディングノート作成に繋がるのではないでしょうか。
若い人向けエンディングノート
エンディングノートというと、どうしても高齢者が人生の終末期に備えて書くものというイメージが強いかもしれません。しかし、実際には若い世代の方々にとっても、エンディングノートを作成することには多くの意義があります。
若い人向けのエンディングノートは、必ずしも「死」を前提としたものではありません。むしろ、これからの人生をより豊かに、そして安心して過ごすためのツールとして活用できます。例えば、自分の夢や目標、大切にしている価値観などを書き出すことで、自己分析を深め、将来のキャリアプランやライフプランを具体的に描くきっかけになります。
また、万が一の不測の事態に備えるという意味合いも持ちます。若くても、事故や急病といった予期せぬ出来事が起こる可能性は誰にでもあります。そのような時に、自分の大切な情報(例えば、銀行口座の情報、SNSアカウントの管理方法、親しい友人の連絡先など)や、医療に関する希望(アレルギー情報や臓器提供の意思など)をまとめておけば、家族や周りの人が困惑するのを防ぐことができます。
特にデジタル情報に関しては、若い世代ほど多くのサービスを利用している傾向があるため、IDやパスワード、データのバックアップ方法などを整理しておくことは、デジタル遺品の問題を考える上でも役立ちます。
若い人向けのエンディングノートでは、記載する項目も柔軟に考えることができます。伝統的な項目に加えて、自分史として楽しかった思い出や経験を記録したり、大切な人への感謝の気持ちを綴ったり、あるいは自分のスキルや知識を整理して誰かに役立ててもらうための情報を残したりすることも考えられます。
エンディングノートを作成する過程で、自分自身と向き合い、これまでの人生を振り返り、そしてこれからの生き方を見つめ直すことは、年齢に関わらず有益な経験となるはずです。若いからまだ早いと考えるのではなく、人生の早い段階から自分の情報を整理し、想いを記録しておくことは、将来の自分自身にとっても、そして大切な人々にとっても価値のあることと言えるでしょう。市販されているエンディングノートの中には、若い世代でも取り組みやすいデザインや構成のものもありますので、気軽に始めてみてはいかがでしょうか。
エンディングノートで始める終活の実践方法
エンディングノートの基本的な知識を得たところで、次に具体的な入手方法や書き方について見ていきましょう。市役所やダイソー、インターネット上でのテンプレートなど、様々な選択肢があります。ご自身に合った方法で、エンディングノート作成を実践してみましょう。
市役所で無料のものはある?
エンディングノートを作成したいと考えたとき、費用をかけずに入手する方法の一つとして、お住まいの市役所や区役所などの自治体が提供しているものがないか調べてみるのも良いでしょう。
近年、終活支援の一環として、一部の自治体では住民向けにオリジナルのエンディングノートを無料で配布したり、ウェブサイト上でテンプレートを無料ダウンロードできるようにしたりしている場合があります。これらのエンディングノートは、その自治体の特性や、高齢者支援の観点から必要な情報が盛り込まれていることが多いです。
市役所などで無料のエンディングノートを入手するメリットとしては、まず費用がかからない点が挙げられます。気軽にエンディングノートを試してみたいという方にとっては、始めやすい選択肢となるでしょう。また、自治体が作成しているという安心感や、地域に根差した情報(例えば、地域の相談窓口の連絡先など)が含まれている可能性もあります。
入手方法としては、自治体の窓口(高齢福祉課など)で直接受け取る、広報誌に挟み込まれて配布される、または自治体の公式ウェブサイトからPDF形式などでダウンロードするといった形が考えられます。関心のある方は、まずはお住まいの自治体のウェブサイトを確認したり、関連部署に問い合わせてみたりすることをお勧めします。
ただし、いくつかの注意点も考慮に入れる必要があります。全ての自治体がエンディングノートを提供しているわけではありませんし、提供している場合でも、その内容は自治体によって異なります。市販のエンディングノートに比べて項目が少なかったり、デザインがシンプルであったりすることもあります。ご自身が書きたい内容や求める機能によっては、自治体のものが必ずしも最適とは限らないかもしれません。
したがって、市役所などで無料のエンディングノートが見つかった場合でも、まずはその内容を確認し、ご自身の目的やニーズに合っているかどうかを検討することが大切です。もし合致するようであれば、有効な選択肢の一つとして活用できるでしょう。
ダイソーのノートも活用できる
エンディングノートは、必ずしも専用のものを購入しなければならないわけではありません。より手軽に、そして費用を抑えて始めたい場合には、100円ショップのダイソーなどで販売されている一般的なノートを活用することも十分に可能です。
ダイソーをはじめとする100円ショップでは、様々なサイズや罫線の種類のノートが手に入ります。これらのノートをエンディングノートとして利用する最大のメリットは、何と言ってもその費用の安さと入手のしやすさでしょう。数百円も出せば、数冊購入することも可能ですし、思い立った時にすぐに書き始めることができます。
普通のノートをエンディングノートとして使う場合、記載する項目は自分で考える必要があります。市販の専用エンディングノートのように、あらかじめ項目が印刷されているわけではないため、どのような情報を残したいのか、どのような構成にするのかを自分で設計する手間はかかります。しかし、これは逆に言えば、完全に自由に、自分の書きたいことだけを書けるというメリットにもなります。既存のフォーマットに縛られず、自分だけのオリジナルなエンディングノートを作成できるのです。
例えば、ノートの最初の数ページを目次として確保し、そこに「個人情報」「医療・介護」「財産」「葬儀」「メッセージ」といったように、自分で考えた項目と対応するページ番号を書き込んでいく方法があります。また、ルーズリーフタイプのノートを選べば、後からページを追加したり、順番を入れ替えたりすることも容易になり、柔軟性が高まります。
ただし、普通のノートを使用する際にはいくつかの点を考慮しておくとよいでしょう。まず、長期間保存することを考えると、紙質や製本がしっかりしたものを選ぶ方が安心です。また、何冊にも分かれてしまうと管理が煩雑になる可能性があるため、ある程度のページ数があるノートを選ぶか、1冊にまとめる工夫をするとよいかもしれません。
ダイソーなどのノートは、エンディングノート作成の第一歩として、気軽に試してみるには非常に適した選択肢です。まずは簡単なことから書き始めてみて、もし必要に応じてより詳細な項目が記載された専用ノートに移行するというのも一つの方法と言えるでしょう。
おすすめの見本とその選び方
エンディングノートを書き始めようと思っても、何から手をつけてよいかわからない、どのような項目を立てればよいか迷う、という方も少なくありません。そのような場合には、市販されているエンディングノートの見本や、インターネット上で提供されているテンプレートを参考にすると、スムーズに作成を進めることができます。ここでは、おすすめの見本やその選び方のポイントについて解説します。
エンディングノートの見本は、大きく分けて市販の冊子タイプのものと、インターネット上でダウンロードできるデジタル形式のものがあります。
市販のエンディングノート
書店や文具店、オンラインショップなどでは、様々な種類のエンディングノートが販売されています。これらの市販ノートは、専門家が監修していたり、利用者の声をもとに改良されていたりするため、必要な項目が網羅的に整理されていることが多いのが特徴です。 選び方のポイントとしては、まずご自身の目的に合ったものを選ぶことが挙げられます。
- 自分史や思い出をじっくり書きたい方: 自分史のページが充実しているものや、フリースペースが多いタイプが適しています。年表が付いているものも、人生を振り返りやすいでしょう。
- 家族への情報伝達を重視する方: 財産、医療、介護、葬儀などの項目が詳細に記載できるタイプや、連絡先リストなどが充実しているものが役立ちます。
- 終活のノウハウも学びたい方: 終活に関するコラムや解説が付いているノートは、書き進めながら知識も得られます。 また、文字の大きさや行間の広さ、ノートの開きやすさなど、実際に書きやすいかどうかも確認するとよいでしょう。
無料でダウンロードできるテンプレート
インターネット上では、自治体やNPO法人、企業などがエンディングノートのテンプレートを無料で提供していることがあります。これらはPDF形式やWord、Excel形式でダウンロードでき、印刷して手書きしたり、パソコンで直接入力したりすることが可能です。 無料テンプレートを選ぶ際は、提供元が信頼できるか、必要な項目が含まれているかを確認することが大切です。シンプルなものから詳細なものまで様々ですので、いくつか見比べてみるとよいでしょう。
どちらのタイプを選ぶにしても、まずは中身をよく見て、ご自身が「これなら書けそう」「これが必要」と感じるものを選ぶことが肝心です。見本はあくまで参考であり、全ての項目を埋めなければならないわけではありません。書きやすい項目から、ご自身のペースで取り組むことが長続きのコツです。いくつか見本を比較検討し、自分にとって最適な一冊(またはテンプレート)を見つけてみてください。
Excelで無料ダウンロードできるシンプルな型
エンディングノートをデジタルデータとして作成・管理したいと考える方にとって、Excel(エクセル)形式の無料テンプレートは非常に便利な選択肢となります。インターネット上では、個人や団体が作成した様々なExcel形式のエンディングノートテンプレートが無料でダウンロードできることがあります。
Excelでエンディングノートを作成する主なメリットは、編集の容易さと管理のしやすさです。手書きと違い、何度でも修正や追記が簡単に行えます。また、パソコンやクラウドストレージに保存しておけば、紛失のリスクを減らし、必要な時にすぐにアクセスできます。文字の大きさやフォントも自由に変更できるため、自分が見やすいようにカスタマイズすることも可能です。
シンプルな型のExcelテンプレートは、必要最低限の項目に絞られていることが多く、初めてエンディングノートを作成する方でも取り組みやすいでしょう。基本的な個人情報、連絡先、医療情報、資産概要といった項目が整理されており、迷わずに記入を進められます。また、Excelの基本的な操作ができれば、自分で項目を追加したり、不要な項目を削除したりといったカスタマイズも容易に行えます。
無料ダウンロードできるExcelテンプレートを探す際には、信頼できるウェブサイトから入手することが大切です。自治体や公的機関、終活関連のNPO法人などが提供しているものであれば、比較的安心して利用できるでしょう。検索エンジンで「エンディングノート Excel 無料 シンプル」といったキーワードで検索すると、多くの選択肢が見つかるはずです。
ただし、Excelでエンディングノートを作成・管理する際には、いくつかの注意点も認識しておく必要があります。まず、パソコンの操作にある程度慣れていることが前提となります。また、デジタルデータであるため、データの消失リスク(ハードディスクの故障など)や、セキュリティ(不正アクセスやウイルス感染など)にも注意を払わなければなりません。定期的なバックアップや、パスワード設定などの対策を講じることが求められます。
そして、最も重要なのは、作成したエンディングノートの存在と保管場所を信頼できる家族に伝えておくことです。せっかく作成しても、いざという時に見つけてもらえなければ意味がありません。Excelファイルにパスワードを設定した場合は、そのパスワードも安全な方法で伝えておく必要があります。
Excelの無料テンプレートは、手軽に始められ、かつ柔軟に管理できるエンディングノート作成方法の一つです。ご自身のITスキルや管理方法に合わせて、上手に活用してみてはいかがでしょうか。
ライフストーリーを使ってあなたの人生を記録してみませんか
「ライフストーリー」とは家族や家系の記憶をあなたが次世代へ受け継ぐことができるサービスです。
遺書や遺言書とは異なる新しい形のエンディングノートです。
無料プランも用意されておりますので、まずは登録して使ってみてください!
\無料登録はコチラから/
概略:エンディングノートで始める終活|基本と実践方法を徹底解説のまとめ
この記事を通じて、エンディングノートの基本的な役割から具体的な書き方、入手方法まで、様々な情報に触れてきました。終活の一環としてエンディングノートを作成することは、ご自身の人生を振り返り、これからの生き方を見つめ直す良い機会となるだけでなく、残される家族への負担を軽減し、想いを伝えるための大切な準備となります。
以下に、エンディングノート作成を始めるにあたっての重要なポイントを改めてまとめます。
エンディングノート作成は、決して難しいことではありません。この記事で得た知識を参考に、まずは最初の一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。それは、あなた自身のため、そしてあなたの大切な人々のために、きっと価値のある時間となるはずです。
