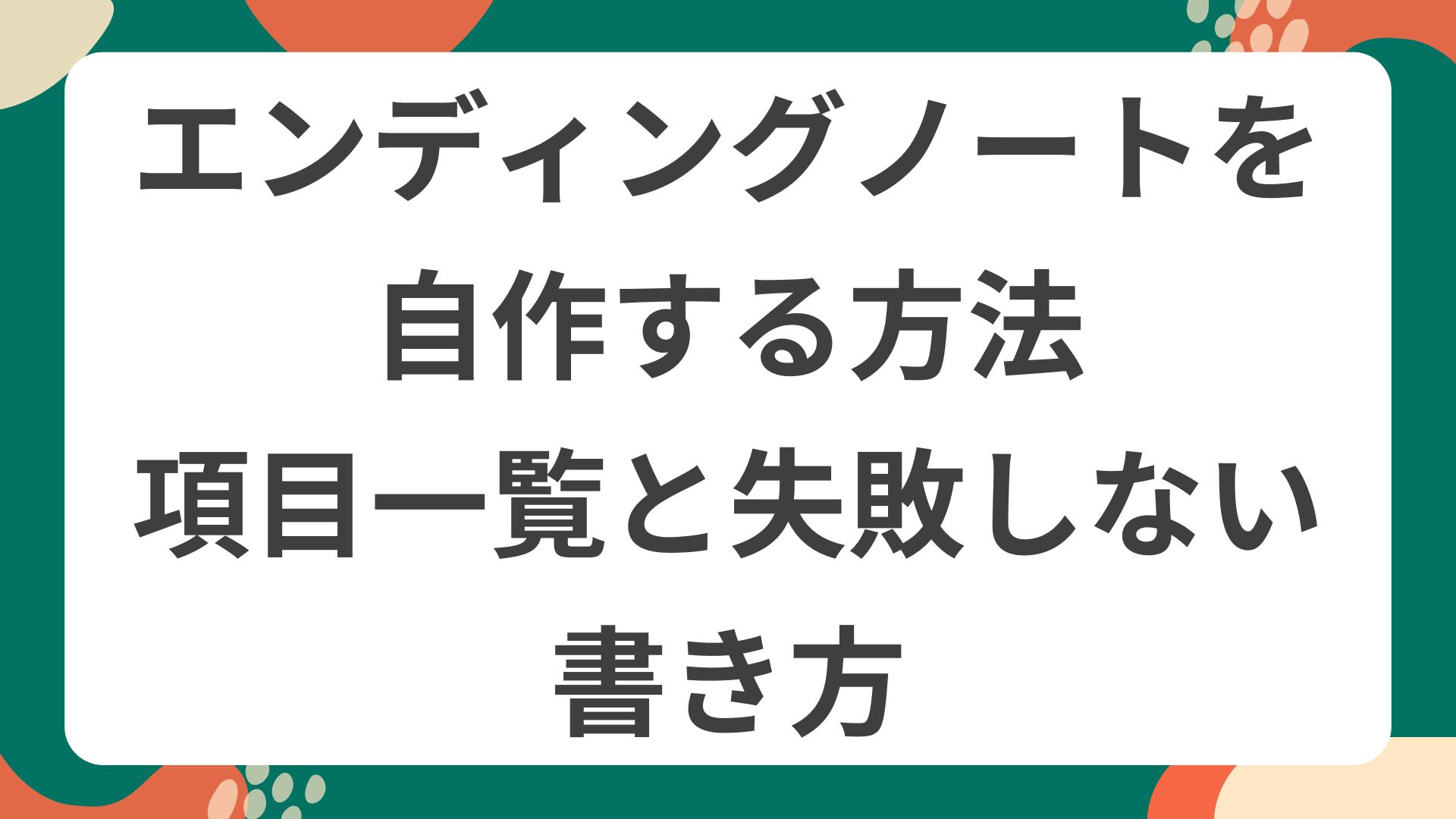
「エンディングノートを自作したいけれど、どんな項目をどのように書けば良いのだろう?」とお考えではありませんか。ご自身の終活に向けて、あるいは万が一の時に備えて、手作りでエンディングノートを作成しようと思い立ったものの、いざ書くとなると具体的な作り方や書くべき項目は何か、悩んでしまうことは少なくありません。特に、若い人向けの項目や、残される子供が助かるエンディングノートの書き方など、ご自身の状況に合わせた内容を盛り込みたいものです。
この記事では、エンディングノートを自作する際の項目一覧をはじめ、参考にできる見本や具体的な記入例の考え方、無料で作成する方法に至るまで、網羅的に解説します。また、エンディングノートが遺言書になるのか、そして完成率はどの程度なのかといった、よくある疑問にもお答えします。この記事を読み進めることで、エンディングノートの自作に関する不安や疑問が解消され、あなただけの特別な一冊をスムーズに作成できるようになるでしょう。
記事のポイント
- 自作エンディングノートに記載すべき具体的な項目
- 手作りでエンディングノートを作成する手順とコツ
- エンディングノート作成時の注意点と法的効力の有無
- 状況別(若い世代や子供がいる場合など)の項目選びのヒント
エンディングノートを自作する時の項目:選び方入門
このセクションでは、自作エンディングノートの基本的な作成方法から、どのような項目を盛り込むべきか、そして無料で作成する方法まで、具体的なステップを解説します。
手作りエンディングノートの簡単な作り方
エンディングノートを手作りで作成する際には、まず全体の流れを把握することが大切です。ご自身の思いを形にするための第一歩として、具体的な作成手順について見ていきましょう。
必要なものを準備する
まず、エンディングノートの母体となるノートを選びます。市販の専用ノートも便利ですが、手作りの場合は大学ノートやルーズリーフ、デザインにこだわったお気に入りのノートなど、自由に選べます。書き直しやページの追加・削除を考慮するなら、バインダー式のルーズリーフが便利かもしれません。筆記用具も、ご自身が書きやすいものを用意しましょう。長く残すものですから、消えにくいインクのペンを選ぶと良いでしょう。
大まかな構成と項目を決める
次に、どのような内容を盛り込みたいか、大まかな構成と記載する項目を考えます。市販のエンディングノートの目次を参考にしたり、インターネットで情報収集したりするのも一つの方法です。この段階では完璧を目指す必要はなく、思いつくままに書き出してみることをおすすめします。後から整理したり、追加したりすることも可能です。
家族と話し合いながら進める
エンディングノートはご自身のためだけではなく、残される家族にとっても重要なものです。可能であれば、作成の過程で家族と話し合い、どのような情報が必要か、どのようなことを知りたいかなどを共有しながら進めると、より実用的なエンディングノートになります。家族の意見を聞くことで、ご自身では気づかなかった必要な項目が見つかることもあります。
少しずつ書き進め、定期的に見直す
全ての項目を一度に完璧に書き上げる必要はありません。書きやすい項目から少しずつ筆を進め、時間をかけて内容を充実させていきましょう。生活状況や考え方は時間とともに変化するため、年に一度など定期的に内容を見直し、必要に応じて加筆修正することが、エンディングノートを常に最新の状態に保つための鍵となります。
手作りエンディングノートの作成は、ご自身の人生を振り返り、未来について考える良い機会にもなります。焦らず、ご自身のペースで取り組むことが何よりも大切です。
書くべき項目は?必須の項目一覧
エンディングノートを手作りする際、どのような情報を記載すれば良いのか迷うかもしれません。ここでは、一般的に入れておくと良いとされる基本的な項目を一覧でご紹介します。これらを参考に、ご自身に必要な項目を選び、オリジナルのエンディングノートを作成してください。
自分自身の基本情報
これはエンディングノートの基礎となる部分です。
- 氏名、生年月日、本籍地、現住所、連絡先(電話番号、メールアドレスなど)
- 血液型、マイナンバー、運転免許証番号、パスポート番号、健康保険証番号など
- 学歴、職歴、資格
- 趣味、特技、好きなこと、大切な思い出
- 自分史(任意ですが、人生を振り返る良い機会になります)
医療・介護に関する情報
万が一の病気やケガ、介護が必要になった場合に備えて、ご自身の意思を明確に伝えておくことは非常に重要です。
- かかりつけ医、持病、既往歴、アレルギー、常備薬
- 延命治療の希望の有無(尊厳死の意思表示など)
- 臓器提供・献体の意思
- 希望する介護の場所(自宅、施設など)や内容
- 介護費用についての考え(利用できる資産など)
財産に関する情報
相続や手続きをスムーズに進めるために、財産状況を正確に記載しておくことが求められます。
- 預貯金(銀行名、支店名、口座番号、種類)
- 不動産(所在地、種類、名義など)
- 有価証券(株式、投資信託など)
- 生命保険・損害保険(保険会社名、証券番号、受取人など)
- 年金(種類、基礎年金番号など)
- ローン・借入金(借入先、残高、返済方法など)
- その他貴重品(貴金属、美術品など)
- クレジットカード情報、電子マネー情報
葬儀・お墓に関する情報
ご自身の最期に関する希望を具体的に記しておくことで、残された家族の負担を軽減できます。
- 希望する葬儀の形式(一般葬、家族葬、直葬など)や規模
- 宗教・宗派、菩提寺の情報
- 遺影に使ってほしい写真の保管場所
- 葬儀に呼んでほしい人、連絡してほしい人のリスト
- お墓の所在地、種類(納骨堂、樹木葬など希望も含む)
- 埋葬方法に関する希望(散骨など)
遺言書・相続に関する情報
エンディングノート自体に法的な拘束力はありませんが、遺言書の有無や保管場所を記しておくことは大切です。
- 遺言書の有無、作成年月日、種類(自筆証書、公正証書など)
- 遺言書の保管場所、または作成を依頼した専門家(弁護士、司法書士など)の連絡先
- 相続に関する基本的な考えや希望(法的な効力はないことを理解した上で)
その他
上記以外にも、伝えておきたいことは多岐にわたるでしょう。
- 大切な人へのメッセージ(家族、友人などへ)
- ペットに関する情報(名前、種類、世話の仕方、引き取り先の希望など)
- パソコンやスマートフォンのパスワード、SNSアカウント情報
- デジタル遺品の取り扱いに関する希望
- 友人・知人の連絡先リスト
- 形見分けに関する希望
これらの項目はあくまで一例です。ご自身の人生や状況に合わせて、必要な情報を追加したり、不要な項目を省略したりして、最適なエンディングノートを作成することが肝要です。
具体的な終活の項目はこれ!
終活の一環としてエンディングノートを作成する場合、特に意識して盛り込みたい項目があります。ここでは、終活という観点から重要度が高いと考えられる具体的な項目について解説します。これらの情報を整理しておくことで、ご自身の最期に向けての準備が整い、残される家族の負担を軽減することにつながります。
葬儀に関する詳細な希望
前述の通り、基本的な葬儀の希望を記載することは大切ですが、終活においてはさらに踏み込んだ内容を検討すると良いでしょう。
- 葬儀社との生前契約の有無と詳細: もし特定の葬儀社と生前契約を結んでいる場合は、契約内容や連絡先、契約書の保管場所を明記します。これにより、家族が葬儀社選びに迷うことなく、スムーズに手続きを進められます。
- 葬儀費用に関する手配: 葬儀費用の準備状況や、どの資産から充当してほしいかなどを記載しておくと、家族の経済的な不安を和らげることができます。
- 弔辞をお願いしたい人: もし弔辞を読んでほしい方がいる場合は、その方のお名前と連絡先を記しておくと、故人の意思を尊重した式典が実現しやすくなります。
- BGMや献花などの細かな希望: 葬儀の雰囲気に関する希望があれば、具体的に書き留めておくのも良いでしょう。
お墓や納骨に関する具体的なプラン
お墓や納骨方法についても、ご自身の明確な意思を示しておくことが望まれます。
- お墓の生前契約の有無と詳細: お墓を既に購入している、あるいは永代供養の契約をしている場合は、その場所、連絡先、契約内容を詳細に記録します。
- 納骨先の詳細情報: 墓地の名称、所在地、区画番号などを正確に記載することで、納骨が滞りなく行われます。
- 分骨や散骨などの希望: 特定の場所に分骨してほしい、海洋散骨や樹木葬を希望するなど、具体的な希望があればその旨と、可能であれば業者名なども記載しておくと、家族が対応しやすくなります。
相続財産の明確化と意思表示(法的効力はないことを前提に)
エンディングノートには直接的な法的効力はありませんが、相続に関するご自身の考えを整理し、家族に伝える手段とはなり得ます。
- 全財産のリストアップと評価額の目安: 預貯金、不動産、有価証券だけでなく、美術品や骨董品など、価値のあるものについてリスト化し、おおよその価値を把握しておくことが望ましいです。
- 誰に何を相続してほしいかの希望: 法的な遺言書とは別に、ご自身の希望として書き記すことができます。ただし、これが法的に有効な相続指定にならないことは、家族にも理解してもらう必要があります。
- 借金やローンの詳細: プラスの財産だけでなく、負債についても正確に記載することは、相続人が相続放棄を検討する際などに不可欠な情報となります。隠さずに全て書き出すことが大切です。
デジタル遺品の整理と取り扱い方針
近年、デジタル遺品に関するトラブルも増えています。終活の項目として、これらの整理も考えておきましょう。
- 主要なアカウント情報: メール、SNS、ネットバンキング、オンラインストレージなど、主要なアカウントのIDとパスワードの管理方法(エンディングノートに直接書くのはセキュリティ上推奨されないため、保管場所のヒントなど)や、死後の取り扱い(解約、データ削除、特定の人への引き継ぎなど)に関する希望を記載します。
これらの終活項目をエンディングノートに丁寧に記載することで、ご自身の意思が明確になり、残される家族がさまざまな手続きや判断をする際の大きな助けとなるでしょう。
見本を参考に分かりやすい記入例を作成
エンディングノートを手作りする際、項目は決まっても「具体的にどう書けばいいの?」と迷うことは少なくありません。市販のエンディングノートやインターネット上で公開されているテンプレートには、多くの場合、見本や記入例が示されています。これらを参考にすることで、ご自身の情報を整理しやすくなり、より分かりやすいエンディングノートを作成できます。
見本から学ぶべきポイント
エンディングノートの見本や記入例を見るときは、単に内容を真似るのではなく、以下のポイントに注目すると良いでしょう。
- 情報の具体性: どのように書けば、第三者にも正確に情報が伝わるか。例えば、銀行口座であれば銀行名・支店名・口座番号・種類まで記載されているか、不動産であれば所在地や名義人が明確か、などです。
- 表現の分かりやすさ: 専門用語が多用されていないか、誰が読んでも理解できる平易な言葉で書かれているか。
- 整理の仕方: 情報が項目ごとに整理され、見やすいレイアウトになっているか。箇条書きや表が効果的に使われているか。
- 網羅性: 記載すべき情報に漏れがないか。例えば、財産の項目であれば、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金など)も考慮されているか。
分かりやすい記入例を作成するためのコツ
実際にご自身で記入する際には、以下の点を意識すると、誰にとっても分かりやすい内容になります。
- 客観的な事実を正確に: 曖昧な表現を避け、日付や金額、連絡先などは正確に記載します。
- 5W1Hを意識する: 「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「なぜ」「どのように」を意識して書くと、情報が具体的に伝わりやすくなります。例えば、大切な思い出を記す際にも、この点を意識すると生き生きとした記録になります。
- 補足情報を加える: 単に情報を羅列するだけでなく、なぜそう思うのか、どうしてほしいのかといった理由や背景を書き添えることで、ご自身の意思がより深く伝わります。例えば、延命治療を望まない理由や、特定の葬儀形式を希望する背景などを簡潔に記すと良いでしょう。
- 図や表を活用する: 複雑な情報や多くの情報を整理して示す際には、図や表を活用すると視覚的に分かりやすくなります。例えば、家系図や財産の一覧表、年間行事の予定などをまとめるのに有効です。
- 定期的な見直しと更新: 前述の通り、情報は変化します。記入例を作成する際にも、将来的な見直しを前提とし、修正しやすいように余白を設けたり、追記できる形式にしたりする工夫も考えられます。
具体的な記入例のイメージ(「自分史」の項目より)
NG例: 「若い頃は色々あった。」(具体性がなく、何も伝わらない)
OK例: 「自分史 - 心に残る出来事」
- 19XX年X月: 〇〇大学入学。△△サークルに所属し、生涯の友となるA君と出会う。
- 19XX年X月: 初めての海外旅行でヨーロッパへ。特にイタリアの歴史的建造物に感銘を受ける。この経験が後の趣味である歴史研究につながった。
- 20XX年X月: 長女B子が誕生。言葉では言い表せないほどの感動を覚えた。育児は大変だったが、日々の成長を見守ることが何よりの喜びだった。
このように、具体的なエピソードや感情を交えて書くことで、単なる記録ではなく、ご自身の人生の軌跡が伝わる内容になります。見本を上手に活用し、ご自身の言葉で、分かりやすく、そして心に残るエンディングノートを作成してください。
無料でできるエンディングノート作成術
エンディングノートを作成したいけれど、費用はあまりかけたくない、という方もいらっしゃるでしょう。実は、市販の立派なノートを購入しなくても、無料でエンディングノートを作成する方法はいくつかあります。ここでは、手軽に始められる無料の作成術をご紹介します。
大学ノートや手持ちのノートを活用する
最も手軽なのは、家にある大学ノートや使っていない手帳などをエンディングノートとして活用する方法です。
- メリット: 新たに購入する費用がかからず、思い立ったその日から始められます。罫線や方眼など、ご自身が書きやすい形式のノートを選べます。
- デメリット: 項目立てやレイアウトを全て自分で考える必要があります。また、見た目が簡素なため、エンディングノートとしての特別感が薄いと感じる方もいるかもしれません。
- ポイント: 表紙に「エンディングノート」と明記したり、自分で項目ごとにインデックスを付けたりする工夫で、使いやすさや認識しやすさが向上します。
WordやExcelで自作する
パソコン操作に慣れている方であれば、WordやExcelなどのオフィスソフトを使ってエンディングノートのテンプレートを自作する方法もおすすめです。
- メリット: 項目やレイアウトを自由に設定でき、修正や追記も容易です。デジタルデータなので、バックアップも取りやすいでしょう。
- デメリット: パソコンやプリンターが必要です。手書きの温かみは薄れるかもしれません。また、パスワード管理などセキュリティ面に注意が必要です。
- ポイント: 作成したデータは印刷して紙でも保管し、家族に保管場所を伝えておくことが大切です。また、定期的にデータを更新し、最新の状態を保つよう心がけましょう。
自治体などが配布する無料テンプレートを活用する
近年、多くの自治体や関連団体が、エンディングノートの無料テンプレートを配布しています。これらはインターネットからPDF形式などでダウンロードできる場合が多いです。
- メリット: 専門家が監修している場合もあり、必要な項目が網羅されていることが多いです。無料で入手できるため、気軽に試せます。
- デメリット: 自治体によっては住民限定で配布している場合や、デザインの選択肢が少ないことがあります。また、PDF形式の場合は直接編集できず、印刷して手書きする必要があります。
- ポイント: まずはお住まいの自治体のホームページを確認してみましょう。また、複数のテンプレートを比較検討し、ご自身に合ったものを選ぶと良いでしょう。例えば、ペットの情報欄が充実しているもの、医療・介護の項目が詳細なものなど、特色があります。
インターネット上の無料ダウンロードサイトを利用する
企業や個人が作成したエンディングノートのテンプレートを無料でダウンロードできるウェブサイトも多数存在します。
- メリット: デザインや項目のバリエーションが豊富で、自分好みのものを見つけやすいです。WordやExcel形式で編集可能なテンプレートも多くあります。
- デメリット: 情報の信頼性や網羅性は作成元によって異なります。個人情報やセキュリティに関する注意書きなどをよく確認する必要があります。
- ポイント: ダウンロードする際には、運営元が信頼できるかを確認し、ファイル形式(Word、Excel、PDFなど)がご自身の使用環境に合っているかを確認しましょう。書き損じても再入手しやすいという利点もあります。
これらの方法を活用すれば、費用をかけずにエンディングノートの作成を始めることができます。大切なのは、形式にこだわりすぎず、ご自身の思いや情報を確実に残すことです。ご自身に合った方法で、まずは一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
エンディングノートを自作する時の項目:作成時の注意点
エンディングノートを自作する際には、内容の充実はもちろんのこと、いくつかの注意点も押さえておく必要があります。このセクションでは、特に若い世代の方が作成する場合のポイントや、残されるお子さんのために配慮すべき点、そしてエンディングノートの法的な位置づけや完成に向けた心構えについて解説します。
若い人向けのエンディングノート項目
エンディングノートはシニア世代だけのもの、というイメージがあるかもしれませんが、実は若い世代にとっても作成する意義は十分にあります。「まだ早い」と思わずに、万が一の事態に備えたり、ご自身の人生設計を見つめ直したりするきっかけとして活用できるのです。若い人向けのエンディングノートでは、特に以下の項目を意識すると良いでしょう。
デジタル情報に関する項目
現代社会において、スマートフォンやパソコン、インターネット上の各種サービスは生活に不可欠です。若い世代ほど多くのデジタル情報を保有している傾向にあります。
- アカウント情報とパスワードの管理: SNS、オンラインバンキング、サブスクリプションサービスなど、利用しているサービスのIDやパスワードの管理方法(直接書き込むのではなく、安全な管理場所のヒントなど)や、万が一の際の取り扱い(解約、データ保存、通知してほしい友人など)に関する希望を明記します。
- デジタル資産の取り扱い: オンライン上の写真や動画、作成したコンテンツ、仮想通貨など、デジタル資産の存在と、それらをどうしてほしいかを記載します。
- デバイスのロック解除方法: スマートフォンやパソコンのロック解除方法(またはそのヒント)を信頼できる人にのみ伝わる形で残しておくと、必要な情報へのアクセスが可能になります。
将来の夢や目標、価値観
若い世代のエンディングノートは、「終末」を意識するだけでなく、これからの人生をより豊かに生きるためのツールとしての側面も持ちます。
- キャリアプランやライフプラン: 将来どのような仕事に就きたいか、どのような生活を送りたいかといった目標を書き出すことで、自己分析や目標設定に役立ちます。
- 大切にしている価値観や信条: ご自身が何を大切にして生きているのかを言葉にすることで、人生の指針が明確になります。
- 万が一、夢半ばで倒れた場合の思い: もしもの時に、ご自身の夢や志を誰かに伝えたい、あるいは託したいといった思いがあれば、その旨を記しておきましょう。
健康情報と緊急連絡先
事故や急病は年齢に関わらず起こり得ます。
- アレルギー情報やかかりつけ医: 特に重要な健康情報は、いつでも誰かが見てわかるようにしておくことが大切です。
- 親族以外の緊急連絡先: 勤務先や親しい友人など、家族以外にも連絡を取ってほしい人の情報を記載します。
- 加入している保険情報: 生命保険や医療保険、傷害保険などの情報をまとめておくと、万が一の際に手続きがスムーズに進みます。
資産状況(特にローンや奨学金など)
若い世代でも、住宅ローンや自動車ローン、奨学金の返済など、負債を抱えている場合があります。
- 借入金やローンの詳細: 借入先、金額、返済状況などを正確に記載します。これは、万が一の際に家族が状況を把握し、対応するために不可欠です。
- 少額でも預貯金や投資の情報: 学生であっても、アルバイト代を貯めた口座や、少額から始めた投資などがあれば記載しておきましょう。
若い世代がエンディングノートを作成することは、決してネガティブなことではありません。むしろ、ご自身の情報を整理し、将来について考える良い機会となります。今の自分に必要な項目を選び、気軽に始めてみることが大切です。
子供が助かるエンディングノートの書き方
ご自身に万が一のことがあった場合、残されるお子さんへの影響は計り知れません。エンディングノートを作成する際に、お子さんのことを思い、情報を整理しておくことは、残されたお子さんや養育者にとって大きな助けとなります。ここでは、特に小さなお子さんがいる場合に配慮したいエンディングノートの書き方について解説します。
子供に関する基本情報
まず、お子さんに関する基本的な情報をまとめておきましょう。
- 氏名、生年月日、アレルギー、かかりつけ医、予防接種の記録など: 特に健康に関する情報は、養育者が変わる場合に非常に重要です。
- 通っている学校や保育園、習い事の情報: 連絡先、担任の先生の名前、月謝の支払い方法などを記載します。
- 仲の良い友達やその保護者の連絡先: 子供の交友関係を把握しておくことは、精神的な支えにもつながります。
子供の将来に関する希望や考え
お子さんの将来について、ご自身の希望や考えを記しておくことも大切です。
- 教育方針や進学に関する希望: どのような教育を受けさせたいか、どのような大人になってほしいかといった願いを綴ります。
- 学資保険や教育資金の準備状況: お子さんのための資金計画があれば、その詳細を記載し、通帳や証券の保管場所を明記します。
- 未成年の場合の親権者や後見人の指定に関する考え: 法的な効力はありませんが、ご自身の希望として、誰にお子さんの養育を託したいかを記しておくことは、関係者が話し合う上での一つの指針となります。可能であれば、事前にその方と話し合っておくことが望ましいです。
子供へのメッセージ
言葉では伝えきれない愛情や思いを、手紙やメッセージとして残しましょう。
- 愛情を伝える言葉: お子さんへの愛情をストレートに表現します。
- 思い出話: 一緒に過ごした楽しい思い出や、お子さんの成長を感じた瞬間などを具体的に書き記します。
- 将来への励ましやアドバイス: お子さんが人生の岐路に立ったときに、心の支えとなるような言葉を贈ります。
- 写真やビデオの整理: 思い出の写真やビデオの保管場所や、デジタルデータの場合はアクセス方法などを記載し、お子さんがいつでも見返せるようにしておくと良いでしょう。
子供の生活に関わる実務的な情報
日々の生活に必要な情報も整理しておくと、養育者の負担を軽減できます。
- 子供の好きな食べ物、嫌いな食べ物、生活習慣(就寝時間など): 細かいことでも、子供の生活リズムを維持するために役立ちます。
- お気に入りのおもちゃや絵本: 子供の心の安定につながるものを記載します。
- 子供名義の預金通帳や印鑑の保管場所:
エンディングノートを通じて、お子さんへの深い愛情と将来への願いを伝えることは、万が一の時だけでなく、お子さんが成長していく過程での心の拠り所にもなり得ます。お子さんの年齢や状況に合わせて、記載する内容を工夫し、温かいメッセージを添えることを心がけてください。
エンディングノートは遺言書になるか?
エンディングノートを作成する際に多くの方が疑問に思うことの一つが、「エンディングノートは遺言書としての効力を持つのだろうか?」という点です。この点を正しく理解しておくことは、ご自身の意思を法的に有効な形で残すために非常に大切です。
エンディングノートと遺言書の基本的な違い
まず、エンディングノートと遺言書は、その目的と法的な位置づけが根本的に異なります。
エンディングノートに法的拘束力はない
結論から申し上げますと、エンディングノートには、原則として遺言書のような法的拘束力はありません。エンディングノートに「長男に全財産を相続させる」と書いたとしても、それだけでは法的に有効な遺言とは認められず、相続人間での遺産分割協議が必要になるのが一般的です。
法律で定められた方式(例えば、自筆証書遺言であれば全文・日付・氏名を自書し押印する、など)に従って作成されていない限り、ご自身の死後の財産の行方や身分に関する事項について、法的な効力を持たせることはできません。
なぜ遺言書が必要なのか
ご自身の意思通りに財産を分配したい、あるいは特定の相続人に多く財産を残したい、相続人以外の人(お世話になった人など)に財産を遺贈したいといった明確な希望がある場合には、エンディングノートとは別に、法的に有効な遺言書を作成する必要があります。
遺言書がない場合、相続は法律の定める相続分(法定相続分)に従って行われるか、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって決定されます。この遺産分割協議がまとまらないと、家庭裁判所での調停や審判に移行することもあり、家族間に争いが生じる可能性も否定できません。
エンディングノートの役割
法的拘束力がないとはいえ、エンディングノートが無意味というわけでは決してありません。エンディングノートは、ご自身の考えや希望を家族に伝えるための重要なコミュニケーションツールとなります。
- 遺言書を作成している場合、その存在や保管場所をエンディングノートに記しておくことで、家族がスムーズに遺言書を見つけ出す手助けになります。
- 財産リストや保険情報などを整理しておくことで、相続手続きに必要な情報を集める手間を省けます。
- 葬儀やお墓に関する希望、延命治療に関する意思などを伝えることで、残された家族が判断に迷う際の指針となり、精神的な負担を軽減できます。
- 家族への感謝の気持ちやメッセージを綴ることで、心のつながりを再確認できます。
したがって、エンディングノートと遺言書は、それぞれの役割を理解した上で、両方準備しておくことが理想的と言えるでしょう。エンディングノートでご自身の広範な思いを伝え、遺言書で法的に効力を持たせたい事項を定める、という使い分けが考えられます。もし遺言書の作成を検討される場合は、専門家(弁護士や司法書士など)に相談することをおすすめします。
エンディングノートの完成率は?
「エンディングノートを書き始めたけれど、なかなか最後まで書ききれない」「途中で挫折してしまわないか心配」といった声を耳にすることがあります。エンディングノートの「完成率」という明確な統計データがあるわけではありませんが、最後まで書き上げることが難しいと感じる方がいるのは事実のようです。しかし、いくつかのポイントを押さえることで、無理なく作成を進め、ご自身の納得のいく形でエンディングノートを形にすることが可能になります。
完成にこだわらない気楽さを持つ
まず大切なのは、「完璧なエンディングノートを一度で完成させなければならない」というプレッシャーを感じすぎないことです。エンディングノートは、ご自身のペースで、書きたいときに書きたいことを書き足していくものであり、いわば「終わりなき旅」のような側面も持ち合わせています。
- 最初から全ての項目を埋めようとしない: 書きやすい項目、すぐに情報が整理できる項目から手をつけるのが長続きのコツです。
- 空欄があっても気にしない: すぐに思い浮かばないことや、まだ決断できないことは、無理に書く必要はありません。時間をかけて考え、気持ちが固まったときに追記すれば良いのです。
- 「完成」ではなく「更新」と捉える: エンディングノートは一度作ったら終わりではありません。生活状況や考え方は変化するため、定期的に見直し、情報を更新していくことが重要です。「完成させる」というよりは「常に最新の状態に保つ」という意識を持つと、取り組みやすくなるでしょう。
モチベーションを維持する工夫
長期間にわたる作業になることもあるため、モチベーションを維持するための工夫も有効です。
- 目的を明確にする: なぜエンディングノートを作りたいのか、誰に何を伝えたいのか、という目的意識を常に持つことで、作成の意義を見失わずに済みます。
- 手作りの楽しさを活かす: 特に自作する場合、お気に入りのノートや筆記用具を使ったり、イラストや写真を添えたりするなど、作成過程そのものを楽しむ工夫を取り入れると、愛着が湧き、継続しやすくなります。
- 家族と共有する: 前述の通り、作成の過程や内容の一部を家族と共有することで、励まし合ったり、必要な情報を教えてもらえたりと、協力体制が生まれることがあります。ただし、プライベートな内容は無理に見せる必要はありません。
- 小さな目標を設定する: 「今週はこの項目を書いてみよう」「今日は1ページだけ進めよう」といったように、達成しやすい小さな目標を立てることで、達成感を得ながら進められます。
作成をサポートするツールの活用
市販のエンディングノートやテンプレートには、書き方のガイドや項目の解説が付いているものが多く、これらを参考にすることでスムーズに進められる場合があります。また、エンディングノートに関するセミナーやワークショップに参加して、他の人と情報交換をしたり、専門家のアドバイスを受けたりするのも良いでしょう。
エンディングノートの作成は、ご自身の人生と向き合う貴重な時間です。完成率という数字に一喜一憂するのではなく、ご自身のペースで、ご自身の言葉で、大切な情報を残していくというプロセスそのものに価値があると考えられます。無理なく、楽しみながら、あなただけのエンディングノートを育てていってください。
ライフストーリーを使ってあなたの人生を記録してみませんか
「ライフストーリー」とは家族や家系の記憶をあなたが次世代へ受け継ぐことができるサービスです。
遺書や遺言書とは異なる新しい形のエンディングノートです。
無料プランも用意されておりますので、まずは登録して使ってみてください!
\無料登録はコチラから/
概略:エンディングノートを自作する方法:項目一覧と失敗しない書き方のまとめ
エンディングノートをご自身で作成する際に知っておきたい項目やポイントについて解説してきました。最後に、この記事で取り上げた重要な点を箇条書きでまとめます。
