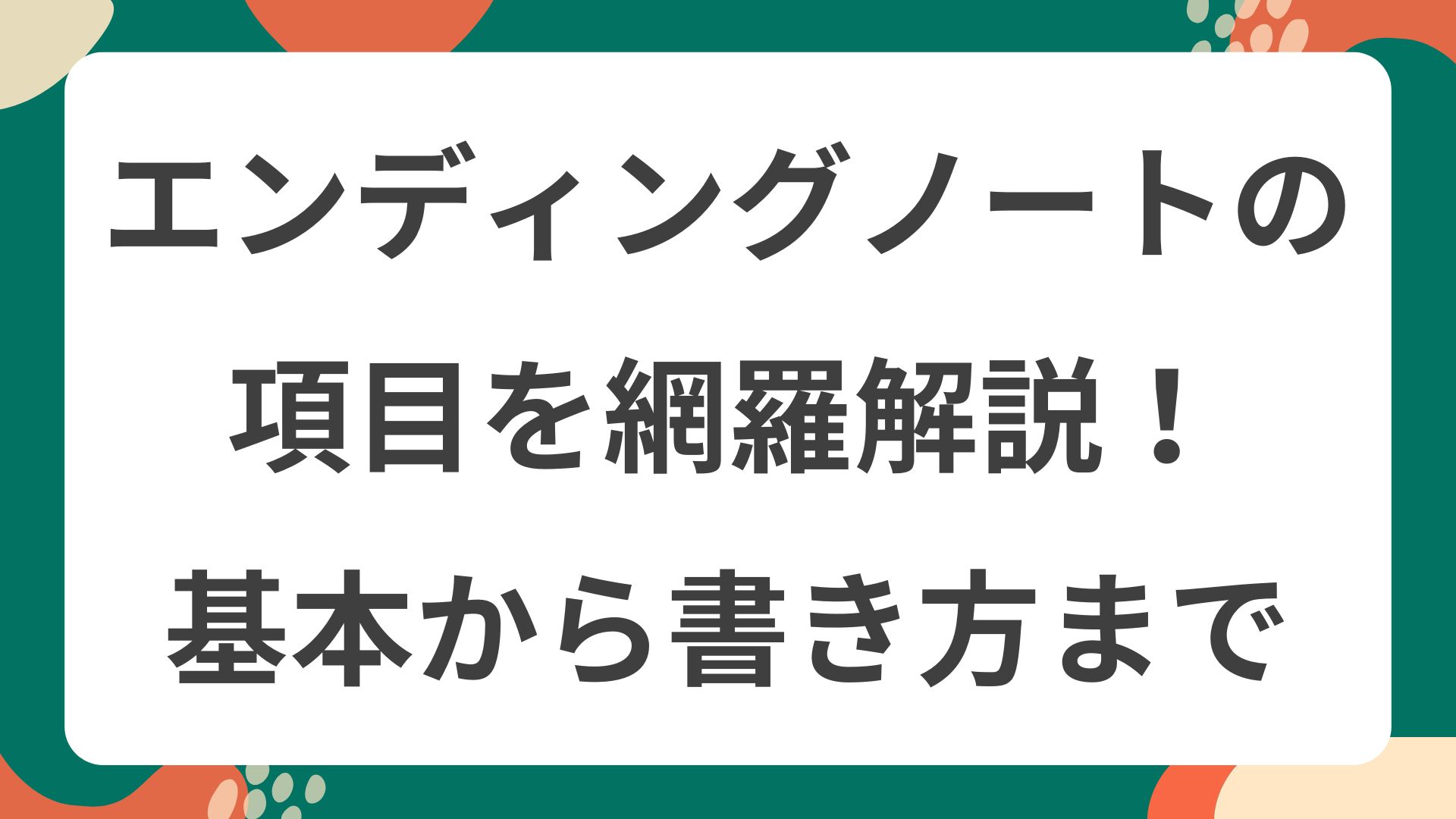
エンディングノートに書くべき項目は何か、終活ノートに何を書けばいいのか、そしてエンディングノートに書く基本情報や具体的に書くべきことは何なのか、とお悩みかもしれません。エンディングノートの作成は、ご自身の情報を整理し、万が一の際に家族の負担を軽減するために非常に役立ちます。しかし、いざ書こうとすると、どのような項目を記載すれば良いのか迷ってしまう方も少なくありません。この記事では、そうした疑問にお答えするため、エンディングノートの記入例や見本を参考にしつつ、自作する場合の項目や手作りの方法、さらには無料で手に入るものやダイソーのような店舗で購入できるエンディングノートについても触れながら、特に若い人向けのエンディングノートに関する情報や、子供が助かるエンディングノートの書き方まで、エンディングノートの項目に関する情報を幅広く解説していきます。
この記事を読むことで、以下の点が明確になります。
記事のポイント
- エンディングノートに記載すべき基本的な項目
- 状況や目的に合わせたエンディングノートの項目の選び方
- エンディングノートを自作する際のポイントや入手方法
- エンディングノート作成時の注意点と活用方法
エンディングノートの項目:基本の理解
エンディングノートに書くべき項目とは
エンディングノートに書くべき項目とは、一言で申し上げるならば「ご自身にもしものことがあった際に、残された家族や大切な人が困らないように伝えたい情報や希望」です。これには、ご自身の基本情報から、財産、医療・介護の希望、葬儀やお墓に関すること、そして大切な人へのメッセージまで、多岐にわたる内容が含まれます。
具体的にどのような項目を設けるべきかについては、市販のエンディングノートや自治体が配布しているテンプレートを参考にするとイメージしやすいでしょう。多くの場合、自分自身の情報(氏名、生年月日、本籍地など)、医療情報(かかりつけ医、持病、アレルギーなど)、財産情報(預貯金、不動産、保険、年金など)、希望する医療や介護の方針、葬儀やお墓の希望、そして家族や友人へのメッセージなどが基本的な項目として挙げられています。
これらの項目を事前に整理し書き留めておくことで、万が一、意思表示ができなくなった場合や亡くなった場合に、ご自身の意思を明確に伝えることができます。それにより、残された家族は手続きや判断に迷うことなく、スムーズに対応を進められるようになります。また、ご自身の人生を振り返り、これからの生き方を見つめ直すきっかけにもなるかもしれません。
エンディングノートには法的な効力はありませんが、ご自身の想いを形にして残すという点で、非常に意義深いものと考えられます。
終活ノートに何を書けばいい?
「終活ノートに何を書けばいいですか?」というご質問は、エンディングノートの作成を考え始めた多くの方が抱く疑問です。前述の通り、エンディングノート(終活ノート)には、ご自身のもしもの時に備えて、家族や友人に伝えたい情報や希望を書き留めます。法的な決まりはないため、基本的には自由に、ご自身が必要だと感じる情報を記載することが可能です。
一般的に終活ノートに記載が推奨される内容としては、まずご自身のプロフィールが挙げられます。氏名、生年月日、住所、連絡先といった基本的な情報に加え、本籍地やマイナンバーなどを記録しておくと、死後の諸手続きがスムーズに進むでしょう。次に、医療や介護に関する希望です。延命治療の意思、臓器提供の希望、希望する介護施設や介護の方針などを具体的に記しておくことで、ご自身の意思を尊重してもらいやすくなります。
財産に関する情報も重要です。預貯金口座、株式や不動産、加入している保険、年金の種類や番号、さらには借入金やローンといった負債についても正確に記載しておきましょう。これにより、相続手続きの際の家族の負担を軽減できます。
葬儀やお墓に関する希望も、多くの方が記載する項目です。希望する葬儀の形式や規模、宗派、遺影に使ってほしい写真、お墓の場所や納骨方法などを具体的に書くことで、残された家族が故人の意向に沿った形で送り出すことができます。
そして、忘れてはならないのが、家族や親族、友人など、お世話になった方々へのメッセージです。普段は照れくさくて伝えられない感謝の気持ちや思い出を綴ることで、心の繋がりを再確認できるでしょう。ペットを飼っている場合は、ペットの情報や世話をお願いしたい人についても記載しておくと安心です。
これらの項目を参考に、ご自身にとって何が大切で、何を伝えておきたいかを考えながら、終活ノートを作成していくことが大切です。
エンディングノートに書くべきことは?
エンディングノートに「書くべきことは?」という問いに対しては、やはり「ご自身の状況や伝えたい想いによって内容は異なるものの、残された方が困らないための情報と、ご自身の希望を明確にすること」が基本になると言えます。法的な拘束力がない自由な形式だからこそ、画一的な正解があるわけではありません。しかし、一般的に多くの方が記載し、かつ残された方にとって有益となる情報には一定の傾向があります。
最低限記録しておきたい情報
まず、客観的な事実として記録しておくべき情報があります。これには、ご自身の基本情報(氏名、生年月日、本籍地、連絡先、マイナンバーなど)、緊急連絡先、健康保険証や介護保険証の番号と保管場所、かかりつけ医や持病、服用中の薬、アレルギー情報などが含まれます。これらの情報は、急な入院時や万が一の際に、迅速かつ適切な対応をしてもらうために不可欠です。
次に、財産に関する情報です。預貯金口座の一覧(銀行名、支店名、口座番号)、有価証券、不動産の詳細、生命保険や損害保険の契約内容、年金の種類と番号、クレジットカードや各種ローンの情報、そしてそれらの関連書類の保管場所を明記しておくことは、相続手続きを円滑に進める上で非常に助けになります。
ご自身の希望を伝える項目
ご自身の意思や希望を伝える項目も重要です。医療・介護に関しては、延命治療や臓器提供の意思、ターミナルケアの希望、介護が必要になった場合の希望(在宅介護か施設介護か、特定の施設があるかなど)を具体的に記載します。
葬儀やお墓については、希望する葬儀の形式(一般葬、家族葬、直葬など)、規模、宗教・宗派、菩提寺の有無、遺影に使ってほしい写真、お墓の所在地や種類(一般墓、納骨堂、樹木葬など)、納骨方法の希望などを記します。誰に連絡してほしいか、誰を葬儀に呼んでほしいかといったリストも役立ちます。
大切な人へのメッセージ
そして、家族や友人、お世話になった方々への感謝のメッセージや、伝えたい想いを自分の言葉で綴ることも、エンディングノートの大切な役割の一つです。思い出話や、これからの人生への願いなどを残すことで、心の繋がりを伝えることができます。
これらの情報を整理し、ご自身の言葉で書き留めていくことで、エンディングノートはより価値のあるものとなるでしょう。
エンディングノートに書く基本情報
エンディングノートに書く基本情報とは、主に「自分自身に関する客観的なデータ」と「各種手続きに必要な情報」を指します。これらの情報は、もしものことがあった際に、家族が各種手続きを進めたり、関係各所に連絡を取ったりする上で、最初の手がかりとなるため、正確かつ分かりやすく記載しておくことが求められます。
自分自身に関する客観的データ
まず、ご自身の氏名、生年月日、現住所、電話番号(固定電話・携帯電話)、そして本籍地を明記します。本籍地は、死亡届の提出や相続手続きの際に戸籍謄本が必要となるため、正確に記載しておくと家族の負担が軽減されます。また、血液型や、運転免許証・パスポート・マイナンバーカードといった身分証明書の番号と保管場所も記録しておくと良いでしょう。家族構成や家系図を簡単にまとめておくのも、相続関係を把握する上で役立つ場合があります。学歴や職歴、取得している資格や免許なども、ご自身を振り返る意味合いや、場合によっては遺族が故人を偲ぶ資料として意味を持つこともあります。
各種手続きに必要な情報
次に、各種手続きに直接関わる情報です。健康保険証や介護保険証の記号番号や発行元、保管場所は、医療機関での手続きや介護サービスの利用に際して必要となります。年金手帳の基礎年金番号や加入している年金の種類、証書の保管場所も、年金関連の手続きには欠かせません。 また、インターネットサービスを多く利用する現代においては、パソコンやスマートフォンのログインパスワードの取り扱いや、SNSアカウント、オンラインバンキング、サブスクリプションサービスなどのIDやパスワード、解約方法に関する情報を整理しておくことも、死後の情報整理や不要な支払いを防ぐために重要度が増しています。ただし、パスワードのような機密情報は、エンディングノートに直接記載するのではなく、保管場所を示すに留めるなど、セキュリティ面での配慮も必要です.
これらの基本情報をきちんと整理しておくことで、残された家族は混乱することなく、落ち着いて諸手続きを進めることができるでしょう。
エンディングノートの見本と記入例
エンディングノートを初めて作成する方にとって、どのような形式で、どんな風に書けば良いのかを具体的にイメージするのは難しいかもしれません。そのような場合に役立つのが、エンディングノートの見本や記入例です。これらを参考にすることで、記載すべき項目や記述の深さ、表現方法などについて具体的な手がかりを得ることができます。
見本から学ぶエンディングノートの構成
市販されているエンディングノートや、終活関連の書籍、ウェブサイトなどで紹介されている見本を見てみると、多くの場合、体系的に情報が整理されていることが分かります。例えば、「自分のこと」「医療・介護のこと」「財産のこと」「葬儀・お墓のこと」「大切な人へのメッセージ」といった大きなカテゴリーに分かれ、さらにその中に詳細な記入項目が設けられています。
見本を確認する際は、まず全体の構成を把握し、どのような情報がどのような順番で整理されているのかを見てみましょう。自分にとって必要な項目、不要な項目、あるいは追加したい項目などが見えてくるはずです。
記入例を参考にする際のポイント
記入例は、各項目に対して具体的にどのような内容を書けばよいのかを示すものです。例えば、「医療の希望」という項目であれば、「延命治療は望みません。苦痛を取り除く治療を優先してください」といった具体的な記述例が示されていることがあります。また、「財産」の項目では、預金口座の情報をどのように記載するか(銀行名、支店名、口座種別、口座番号など)が例示されているでしょう。
記入例を参考にする際には、以下の点に注意すると良いでしょう。
- 具体性: 抽象的な表現ではなく、誰が読んでも誤解なく理解できるような具体的な記述がされているか。
- 網羅性: 必要な情報が漏れなく記載されているか。例えば、連絡先であれば氏名だけでなく電話番号や関係性も記載されているかなど。
- 表現のトーン: 事務的な情報だけでなく、感謝の気持ちや個人的な想いを伝える部分では、どのような言葉遣いがされているか。
ただし、見本や記入例はあくまで参考です。ご自身の状況や伝えたい内容に合わせて、自由にアレンジすることが大切です。例えば、ペットを飼っている方であれば、ペットに関する詳細な情報を加える必要があるでしょうし、特定の趣味やコレクションについて書き残したい方もいるかもしれません。
インターネット上には、無料でダウンロードできるエンディングノートのテンプレートや記入例も多数存在します。まずはそういったものをいくつか見比べてみて、ご自身に合ったスタイルを見つけることから始めてみるのがおすすめです。
自分に合うエンディングノートの項目の準備
エンディングノートを自作する時の項目と手作り
エンディングノートは市販品も多数ありますが、ご自身の状況や書きたい内容に合わせて自作することも可能です。自作する最大のメリットは、項目を自由に設定でき、本当に必要な情報だけを盛り込める点にあります。また、手作りすることで、より愛着が湧き、想いを込めて作成できるという方もいらっしゃるでしょう。
自作する際の基本的な項目
エンディングノートを自作する場合でも、基本的な項目は市販品と大きく変わりません。前述の通り、以下のような項目をベースに考えると良いでしょう。
- 自分自身の基本情報: 氏名、生年月日、本籍地、連絡先、マイナンバー、家族構成など。
- 医療・介護の希望: かかりつけ医、持病、アレルギー、延命治療や臓器提供の意思、希望する介護の形など。
- 財産に関する情報: 預貯金、不動産、有価証券、保険、年金、ローンや借金、各種契約サービス(サブスクリプションなど)のID・パスワードの管理方法など。
- 葬儀・お墓の希望: 葬儀の形式・規模、宗教・宗派、遺影写真、納骨方法、墓地の情報など。
- 連絡先リスト: 親族、友人、知人など、もしもの際に連絡してほしい人のリスト。
- ペットに関する情報: ペットの種類、名前、性格、かかりつけ医、世話をお願いしたい人など。
- 大切な人へのメッセージ: 家族や友人への感謝の気持ちや伝えたいこと。
- 自分史・思い出: 人生の記録や楽しかった思い出など。
- これからの計画・やりたいこと: 残りの人生で挑戦したいことや目標。
これらの項目を参考に、ご自身にとって特に重要なもの、伝え残しておきたいことを中心に項目を組み立てていきます。例えば、趣味のコレクションを多くお持ちの方であれば、そのリストや価値、譲りたい相手などを記載する項目を設けるのも良いでしょう。
手作りする方法とポイント
エンディングノートを手作りする方法はいくつかあります。
- 大学ノートやルーズリーフに手書きする: 最も手軽な方法です。自由に書き込める反面、項目立てや整理は自分で行う必要があります。後から追記や修正がしやすいように、ルーズリーフを使用するのも一つの手です。
- パソコンで作成する: WordやExcelなどのソフトを使えば、レイアウトを整えやすく、修正も容易です。作成したデータを印刷してファイルに綴じたり、デジタルデータとして保存したりできます。テンプレートを自作するイメージです。
- 市販の無地ノートをカスタマイズする: お気に入りのノートを選び、自分で項目を書き込んだり、関連する写真や資料を貼り付けたりして、オリジナルのエンディングノートを作成します。
手作りする際のポイントは、まず「何のために、誰に何を伝えたいのか」を明確にすることです。目的がはっきりすれば、おのずと必要な項目も見えてきます。また、一度に全てを完璧に作ろうとせず、書けるところから少しずつ書き進め、定期的に見直して更新していくことが長続きのコツです。情報を整理しやすいように、インデックスを付けたり、色分けしたりするのも有効な工夫と言えます。
自作や手作りのエンディングノートは、ご自身の個性や想いを反映させやすい反面、項目に漏れが生じやすいというデメリットも考慮し、市販のノートの目次などを参考にしながら進めると良いでしょう。
無料エンディングノートとダイソー活用
エンディングノートを作成したいけれど、費用はあまりかけたくない、あるいはまずは手軽に試してみたいと考える方もいらっしゃるでしょう。そのような場合に役立つのが、無料で入手できるエンディングノートのテンプレートや、ダイソーのような100円ショップで手に入るノートを活用する方法です。
無料で入手できるエンディングノート
インターネット上には、様々な団体や企業、自治体などが提供している無料のエンディングノートのテンプレートが数多く存在します。これらは主にPDF形式で提供されており、ダウンロードして印刷すればすぐに使用できるのが大きなメリットです。
無料テンプレートを選ぶ際のポイントは以下の通りです。
- 項目の網羅性: 自分が必要とする項目が十分にカバーされているか確認しましょう。シンプルなものから詳細なものまで様々です。
- デザインやレイアウト: 書き込みやすさや見やすさも重要です。自分が取り組みやすいデザインのものを選びましょう。
- 提供元の信頼性: 可能であれば、信頼できる団体や企業が提供しているものを選ぶと安心です。
多くの無料テンプレートは、基本的な項目(個人情報、医療・介護、財産、葬儀など)は押さえているため、エンディングノートの概要を掴んだり、試しに書いてみたりするには十分と言えます。ただし、無料である分、サポートがなかったり、特定のサービスへの誘導が含まれていたりする場合もあるため、その点は留意しておくと良いでしょう。
ダイソーなどの100円ショップの活用
ダイソーをはじめとする100円ショップでも、エンディングノートとして活用できるアイテムを見つけることができます。
- エンディングノート専用品: 最近では、100円ショップでもエンディングノートとして編集されたノートが販売されていることがあります。項目があらかじめ印刷されており、手軽に始められるのが魅力です。内容はシンプルなものが多いですが、入門用としては十分な場合もあります。
- 一般のノートやファイル: もし専用品が見つからなくても、普通の大学ノートやルーズリーフ、バインダーなどを購入し、自分で項目を書き込んで自作のエンディングノートを作成することも可能です。これならば、費用を抑えつつ、完全に自分仕様のノートを作ることができます。ルーズリーフとバインダーを使えば、ページの入れ替えや追加も自由に行えます。
無料で入手できるテンプレートや、ダイソーなどで手軽に購入できるノートは、エンディングノート作成の第一歩を踏み出すための良いきっかけになります。まずはこれらを利用してみて、自分に必要な項目や書きやすい形式を把握し、より本格的なエンディングノート作成に繋げていくというのも賢明な方法です。大切なのは、完璧を目指すことよりも、まずは書き始めてみることです。
若い人向けエンディングノートの書き方
エンディングノートと聞くと、どうしても高齢者の方が終活の一環として作成するものというイメージが強いかもしれません。しかし、実際には事故や急病など、予期せぬ出来事は年齢に関わらず誰にでも起こり得ます。そのため、若い世代の方がエンディングノートを作成することにも大きな意味があります。若い人向けのエンディングノートでは、高齢者の方とは少し異なる視点や項目が重要になる場合があります。
若い世代がエンディングノートを書く意義
若い方がエンディングノートを書く意義としては、主に以下の点が挙げられます。
- デジタル情報の整理: スマートフォンやパソコン、SNS、オンラインサービスなどのデジタル情報は、若い世代ほど多く利用している傾向にあります。これらのアカウント情報やデータの取り扱い(保存、削除、誰かに引き継ぐかなど)に関する希望を明確にしておくことは非常に重要です。パスワードの管理方法なども含めて記載しておくと、万が一の際に家族が困惑するのを防げます。
- 突発的な事態への備え: 若く健康であっても、不慮の事故や突然の病気に見舞われる可能性はゼロではありません。もしもの場合に備え、医療に関する希望(延命治療、臓器提供など)や、大切な人へのメッセージを残しておくことは、残された家族にとって大きな心の支えとなり得ます。
- 自分自身の人生設計の見直し: エンディングノートを作成する過程で、自分の価値観や目標、人間関係などを見つめ直すことができます。これは、今後の人生をより豊かに生きるための良い機会となるでしょう。
若い人向けの項目と書き方のポイント
若い人向けのエンディングノートで特に意識したい項目や書き方のポイントは以下の通りです。
- デジタル遺産: 前述の通り、各種アカウント情報、データのバックアップ場所、SNSの死後対応(追悼アカウントにするか、削除するかなど)に関する希望を具体的に記載します。
- 友人・知人への連絡: 家族が把握していない友人や知人がいる場合、連絡先リストや、その人たちに伝えてほしいメッセージなどを残しておくと良いでしょう。
- 趣味やコレクション: 大切にしている趣味の道具やコレクションについて、その価値や思い入れ、もしもの場合の処分方法や譲渡先などを記しておくのも一案です。
- これからの夢や目標: 「エンディング」という言葉にとらわれず、これからやりたいこと、達成したい夢などを書き出すことで、未来への希望を記すノートとしての側面も持たせることができます。
- ペット: ペットを飼っている場合は、世話をお願いしたい人や、ペットの詳細な情報(食事、病歴、性格など)を必ず記載しましょう。
- 表現のトーン: あまり重々しくなりすぎず、自分らしい言葉で、率直な気持ちを綴ることが大切です。写真やイラストを添えるのも良いでしょう。
若い世代にとってエンディングノートは、「死への準備」というよりも、「今と未来をより良く生きるためのツール」としての意味合いが強いかもしれません。定期的に見直し、更新していくことで、人生の節目節目で自分自身を振り返る良い習慣にも繋がります。
子供が助かるエンディングノート作成術
ご自身に万が一のことがあった場合、残された子供たちが困らないように、そして少しでも心の負担を軽減できるようにエンディングノートを作成することは、親として非常に大切な準備の一つと言えます。子供が助かるエンディングノートを作成するためには、子供の年齢や状況を考慮し、具体的かつ分かりやすい情報を残すことが鍵となります。
子供のために記載すべき重要な項目
子供、特に未成年の子供がいる場合にエンディングノートに記載しておきたい重要な項目には、以下のようなものがあります。
親権者・後見人の指定に関する希望: もし両親ともに不幸があった場合、未成年の子供の親権者や後見人を誰にお願いしたいか、その理由などを具体的に記載しておきます。これは法的な効力を持つものではありませんが、家庭裁判所が判断する際の重要な参考資料となり得ます。事前に希望する相手と話し合っておくことも大切です。
教育方針や子供への想い: 子供の教育についてどのような考えを持っているか、どのような人に育ってほしいか、そして子供への愛情や感謝の気持ちを具体的に言葉で残しましょう。これは、子供が成長していく上での精神的な支えとなる可能性があります。
学資保険や子供名義の預貯金に関する情報: 子供のための学資保険や預貯金がある場合、その詳細(金融機関名、口座番号、証券番号、保険内容など)と関連書類の保管場所を明確に記載します。これにより、必要な時にスムーズに手続きが進められます。
子供の学校や習い事、友人関係に関する情報: 子供が通っている学校名、学年、クラス、担任の先生の名前、連絡先、習い事の情報、仲の良い友人の名前や連絡先などを記録しておくと、子供の生活をサポートする人が状況を把握しやすくなります。
子供のアレルギーや持病、かかりつけ医の情報: 子供にアレルギーや持病がある場合は、その詳細、対処法、かかりつけの病院や医師の連絡先を必ず記載してください。
大切な思い出や写真の整理: 子供との大切な思い出(旅行、誕生日、行事など)を振り返り、関連する写真やアルバムの場所を記しておくと、子供が親との思い出を辿る手助けになります。
生活に必要な情報: 日常的な生活習慣(起床・就寝時間、食事の好み、好きな遊びなど)や、子供が安心できる言葉かけ、お気に入りのものなどを記録しておくことも、環境が変わった際の子供の精神的な安定に繋がるかもしれません。
子供に伝える際の配慮
エンディングノートの存在を子供に伝えるかどうか、伝える場合はいつ、どのように伝えるかは慎重に考える必要があります。子供の年齢や性格、理解度に合わせて、不安を与えないように配慮することが大切です。場合によっては、信頼できる親族や友人にノートの存在と保管場所を伝えておき、適切なタイミングで子供に渡してもらうという方法も考えられます。
エンディングノートは、親から子への最後のラブレターとも言えるかもしれません。事務的な情報だけでなく、愛情のこもったメッセージを添えることで、子供たちの未来を支える力となるでしょう。
ライフストーリーを使ってあなたの人生を記録してみませんか
「ライフストーリー」とは家族や家系の記憶をあなたが次世代へ受け継ぐことができるサービスです。
遺書や遺言書とは異なる新しい形のエンディングノートです。
無料プランも用意されておりますので、まずは登録して使ってみてください!
\無料登録はコチラから/
概略:エンディングノートの項目を網羅解説!基本から書き方までのまとめ
エンディングノートの作成は、ご自身の人生を整理し、万が一の際に残された家族や大切な人々の負担を軽減するための重要な準備です。この記事を通じて、エンディングノートに記載すべき様々な項目についてご理解いただけたことと思います。最後に、エンディングノートの項目を整理する上で大切なポイントをまとめます。
エンディングノートの項目は多岐にわたりますが、すべてを一度に完璧に書く必要はありません。ご自身のペースで、書けるところから少しずつ書き進めていくことが大切です。この記事が、あなたのエンディングノート作成の一助となれば幸いです。
